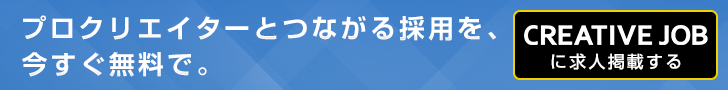2017年秋、渋谷で行われた福祉の展示会「超福祉展」で、自身が主宰するプロジェクトチームが開発したプロダクトを初お披露目し、マスコミに取り上げられて大きな反響を得た『アンドハンド』を手掛けているタキザワケイタさん。ワークショップデザイナーの顔も持ち多彩な才能を発揮して活躍中です。
枠に捉われず自由な発想でクリエイティビティを発揮するタキザワさんにお話を伺いました。
千葉工業大学 工業デザイン学科を卒業後、建築設計事務所、企画会社を経て、2013 年 大手広告代理店へ。 新規事業・商品開発・ブランディング・人材育成・組織開発など、大手企業が抱えるさまざまな課題の解決に向け、ワークショップを実践している。
LINE「LINE BOT AWARDS」グランプリ受賞。Google「Android Experiments OBJECT」2作品グランプリ受賞。宣伝会議「販促企画コンペ」グランプリ受賞。
青山学院大学 ワークショップデザイナー育成プログラム講師・LEGO® SERIOUS PLAY® 認定ファシリテーター
「やさしさから やさしさが生まれる社会」の実現を目指した『アンドハンド』プロジェクト
2017年11月に渋谷の大型商業施設で開催された『超福祉展』という催しで、僕が主宰するプロジェクトチームが手掛けた「アンドハンド」を展示しました。
「アンドハンド」はLINEなどを活用し、身体・精神的な不安や困難を抱えた人と、手助けをしたい人をマッチングし、具体的な行動をサポートするサービスです。
手助けを必要とする人はBeaconデバイスを携帯し、必要な状況でONにすると、周囲のサポーター(手助けをしたい人)のLINEにメッセージが届きます。するとサポーターはChatBotを通じて手助けを必要とする人の状況が分かり、具体的な行動を起こすことができるというものです。デバイスは妊婦、視覚障がい者、聴覚障がい者、車椅子利用者、ヘルプマーク使用者、外国人旅行者向けなどを検討・開発しています。
「アンドハンド」プロジェクトを立ち上げるきっかけとなったのは、マタニティーマーク問題との出会い。マタニティーマークをつけていると、逆に「危険」だとか「お腹を押される」といった問題を取り上げた記事を見たり、実際に妻が子供を妊娠した時の経験から、「このマタニティマーク問題をどうにかしたい」という思いが芽生えました。
 それをカタチにしたのが妊婦さん向けのコンセプトモデルである「スマート・マタニティマーク」。開発のきっかけとなったのは、Google主催のプロジェクト「Android Experiments OBJECT」というコンペティションに、仲間と応募したこと。ワークショップを3回実施し、10のアイデアを応募。2つのアイデアがグランプリを受賞し、その一つが「スマート・マタニティマーク」だったんです。さらには、そのアイデアを展開した「アンドハンド」で「LINE BOT AWARDS」もグランプリを受賞しました。
それをカタチにしたのが妊婦さん向けのコンセプトモデルである「スマート・マタニティマーク」。開発のきっかけとなったのは、Google主催のプロジェクト「Android Experiments OBJECT」というコンペティションに、仲間と応募したこと。ワークショップを3回実施し、10のアイデアを応募。2つのアイデアがグランプリを受賞し、その一つが「スマート・マタニティマーク」だったんです。さらには、そのアイデアを展開した「アンドハンド」で「LINE BOT AWARDS」もグランプリを受賞しました。
現在、大日本印刷さん、東京メトロさん、LINEさんと連携し、12月中旬にメトロ銀座線で実施予定の「妊婦向けサービス実証実験」の準備を進めている所です。これはまだ最初の一歩に過ぎませんが、結果を分析・改善し、より良いサービスにしていきたいです。
また、「超福祉展」で発表した「聴覚障がい者向け」についても、当事者の方からの評判がとても良く、手ごたえをつかむことが出来ました。同時に様々なご要望もいただけたので、今後の開発に活かしていきたいと思います。
社会的課題にアプローチするモノやコトをファシリテートする
僕はもともと建築を学んでいて、大学卒業後に就職したのは設計事務所でした。その後、ワークショップデザイナーとなり、現在は広告代理店で仕事をしながら、個人活動として「アンドハンド」プロジェクトに取り組んでいます。
大学や仕事で建築を学んでいた時に培ったモノづくりや場づくりの感覚が、現在のワークショップデザインやファシリテーションのベースになっています。
 特に最近は、単体のワークショップだけではなく、ワークショップを効果的に活用しながらプロジェクト全体をファシリテーションしていくことを意識しています。
特に最近は、単体のワークショップだけではなく、ワークショップを効果的に活用しながらプロジェクト全体をファシリテーションしていくことを意識しています。
社会の変化が激しく先が見えない状況において、明確なゴールは設定しにくく、かつ変化していく。そのような状況で目指すべきヴィジョンを描き、半歩先のゴールを設定し、そこに向けてメンバーとプロジェクトをファシリテーションしていくのが自分の役割です。
アンドハンドのプロジェクトでもユーザーリサーチ、アイディエーション、企業の巻き込みなど、状況に応じてワークショップを実施することで、プロジェクトをファシリテーションしていきました。
世の中の流れとしても、社会的課題をどうビジネスにつなげていくかというのが、企業にとって大きなテーマの一つだと思います。「アンドハンド」はその領域にチャレンジしていくプロジェクトです。
自分の中の大きな転換ポイントは、「建築家」という専門性の高い領域から、「ワークショップデザイナー」というより開かれた領域で仕事をするようになった点ですね。建築におけるコンセプトや表現、作家性よりも、領域に捉われずに社会に対して新しい価値を提供していきたいと、考えが変化していきました。
ワークショップを「イベント化」せず日常に定着させる取り組み
僕は青山学院大学社会情報学部の大学院で、アイデア発想ワークショップについてeラーニングで教えています。実際に特定の企業・商品を設定し、プロモーションのアイデアを考察するワークショップを実施し、それを撮影・編集したものを教材としました。
映像を見ながら参加者としても体験できる構成にし、ワークショップデザイナー・ファシリテーター・参加者それぞれの視点から学んでもらえるように工夫しました。受講生の方からもとても評判です。
気をつけているのは、ワークショップを特別なイベントにするのではなくて、いかに普段の業務の中にワークショップの要素を取り入れられるかだと思っていて。
ワークショップは楽しいですし、盛り上がりますし、その場で“やった感”は出るものの、一方でどうしても“イベント化”しがちな側面があります。
 よく企業さん向けのワークショップで上がるお悩みに「ワークショップは盛り上がったけど、自分のデスクに戻ると、いつもの仕事が待っている…」というものがあります。普段とのギャップが発生し、逆にモチベーションが下がってしまったり、担当者・責任者が決めるべきことをワークショップで全員で決めようとしたり、ワークショップ疲れや依存になってしまうことが往々にしてあるんです。
よく企業さん向けのワークショップで上がるお悩みに「ワークショップは盛り上がったけど、自分のデスクに戻ると、いつもの仕事が待っている…」というものがあります。普段とのギャップが発生し、逆にモチベーションが下がってしまったり、担当者・責任者が決めるべきことをワークショップで全員で決めようとしたり、ワークショップ疲れや依存になってしまうことが往々にしてあるんです。
なので、プロジェクトを通じてワークショップ手法を学んでもらったり、マインドセット、チームビルディングすることで、僕が抜けた後も社員の皆さん自走できる状態になっていることを意識しています。
そして成果物のクオリティに責任を持つこと。ワークショップはやること自体が目的になりがちですが、根本的には成果物のみで評価されるべきなので、そこにもこだわっていますね。
例えばよくやるのが、3分アイデアソン。出されたテーマについて、3分間個人でアイデア出しをします。3分経ったら次のテーマが出され、また3分でアイデアを出す。これを休憩を挟みながら45分間繰り返し、投票で順位をつけます。
人間は無意識にいろいろと考えているので、それをワークショップ手法で顕在化させることで、アイデアはいくらでも生み出すことができます。
3分アイデアソンを社内で継続開催したことがあるのですが、確実にアイデア発想力、スケッチ力、ネーミングセンス、プレゼン力が向上しました。
なにかを習得しようとした時に、本を読むことから始めることが多いと思いますが、とりあえずやってみて自分の身体で実際に体験してから本を読んだ方が効率的だと思います。「アンドハンド」プロジェクトもそうですが「とりあえずやってみよう!」というマインドが、自身の成長スピードを速めてくれると思います。
また、やってみてうまくいかない方が成長できると思っていて。入念に準備してうまくいくより、失敗しても改善を繰り返しながら同じ場所にたどり着く方が、より成長できると思っています。でも、失敗は大怪我にならない程度に…(笑)。
“ワクワク”のアンテナを張りながら、社会のニーズに、自分のテーマを乗せて、より良い社会をつくる
「アンドハンド」プロジェクトはいろいろな方から共感・応援していただいてここまでたどり着くことができました。このプロジェクトはもはや自分たちのものではなく、応援してくれているみんなのものです。このサービスを必要としている人にきちんと届ける、これが僕のミッションです。
ただ、「弱者のために」「福祉のために」というよりも、その時々で自分が心の底からどうにかしたいと思った問題について、共感する仲間と共創して解決していきたいと思っています。
僕は、多様なプロフェッショナルからなるコ・クリエーションチーム「PLAYERS」を主宰していて、最初のプロジェクトが「アンドハンド」です。PLAYERSのスローガンは「一緒になってワクワクし、世の中の問題に立ち向かう」。
もちろん問題は解決したいけれども、まずは自分たちがワクワクするかどうか?その感覚を大切にしていきたいと思っています。
近い将来、福祉の分野に注力しているかもしれないし、まったく違うことをやっているかもしれない。将来については分からない部分が多い、だからこそいま自分が置かれている状況を観察し、自分のスキルを活かし、新しいテーマを乗せて、とりあえずやってみる―。
どうせやるなら、自分らしく、共感する仲間と、ワクワクするやり方で。
それを企むのが好きなんでしょうね。それが自分らしさかなと思います。

撮影:TAKASHI KISHINAMI インタビュー・テキスト:佐藤由佳 編集:CREATIVE VILLAGE編集部