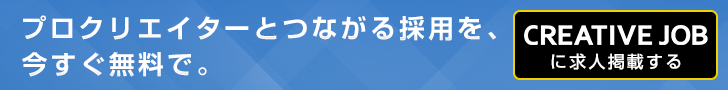2018年に20周年を迎える、ラジオ大阪の大人気アニラジ枠『1314 V-STATION』。その初代プロデューサーを務めた兼田健一郎さんが50歳を機にラジオ大阪を退職し、新会社「株式会社ベルガモ」を設立しました。
本インタビューでは、アニラジの黎明期を支え、根強い人気を作り上げた兼田さんの27年間のキャリアを振り返り、人気ラジオ番組の裏話や、これからラジオ業界に進出する人材に向けてのアドバイスをお伺いします。
1968年大阪府生まれ。兵庫県小野市出身。法政大学社会学部を卒業後、1991年にラジオ大阪に入社。
報道部に配属され、放送記者として大阪府警などを担当。
1993年に東京支社へ転勤し、国会記者を経て、営業部に異動。
以来、『1314 V-STATION(Vステ)』を中心とした各番組のプロデュースを担当。
2004年7月より大阪本社の編成部へと異動し、2018年12月にラジオ大阪を退職。
2019年1月より株式会社ベルガモを設立、代表取締役に就任。
https://bergamo.audio/
『1314 V-STATION』誕生の経緯
――ラジオ大阪の名物プロデューサー「かねやん」と言えば、アニラジ好きの間では有名です。まずは、そんな兼田さんがラジオ局に入られた経緯をお聞かせください。
ジャーナリストになりたくて、新聞社を受け、テレビ局を受け、たまたまラジオ局に入社できたんです。ラジオ大阪は報道部があったから受けただけで、今のアニラジ好きのように「絶対ラジオ局に入るぞ!」という考えはありませんでした。
――ラジオっ子でもなかったと。
いえ、新聞・テレビといったマスメディアの一環として聞いていました。僕が小学生だった時代は、全校集会で「テレビを観てはいけません」と大真面目に言われる時代だったけれど、「ラジオを聞いてはいけません」とは言われませんから。子どもだから世間の風を知りたい気持ちもあったし、クラスメイトと話を合わせるためにもラジオはよく聞いていましたね。

――なるほど。その後は希望通りに報道部に配属となりましたね。
大阪府警の記者クラブに入って最初に取材へ行ったのが、忘れもしない『信楽高原鐵道列車衝突事故』(※1)の現場でした。それ以降は人の生死に関わるニュースをたくさん取材して、平成5年に東京支社へ異動。国会担当として勤めた後、ラジオコマーシャルを扱う営業に転身しました。これが僕の運命の分かれ道になったわけです。
(※1)信楽高原鐵道列車衝突事故…1991年5月14日10時35分頃、滋賀県甲賀郡信楽町(現・甲賀市信楽町)黄瀬の信楽高原鐵道信楽線・小野谷信号場と、紫香楽宮跡駅間の間で発生した事故。42名が死亡、614名が重軽傷を負った。
――というと?
営業職には業種別の担当があって、僕の割振りに「おもちゃ・ゲーム」とあったんです。それで、ある広告代理店さんから「SonyがPlayStationのプロモーションでラジオをやりたがっている」という話が来た時に担当を引き受けました。今も昔もゲームのことなんてさっぱりわからないけれど(笑)。
今にして思えば、これが日本のアニラジが本格的にスタートするきっかけなんですよ。ゲーム&ウオッチのようなピコピコ音だけのゲームと違い、PlayStationはクリアな音声も音楽も入ります。当時はセガサターンの発売が重なったこともあって、声優の需要が爆発的に高まりました。声優という仕事はだいぶ前からあったけれど、それまではおもちゃ販売のためのアニメーションだったでしょ。それが、ゲームというマーケットが増えたことで声優に注目が集まるようになったんです。そこに声優とラジオのマッチングの良さが重なって、アニラジが繁盛する構造ができあがりました。
そんな時代だから、『國府田マリ子のGAME MUSEUM』がスタートしてからは毎クールごとに番組が増え、ラジオ大阪としても「これをブランディングしていくべき」という流れになりました。そうして生まれたのが『1314 V-STATION』です。その後は『宮村優子の直球で行こう!』などの番組がヒットして、21世紀が来るまでは本当に良い思いをさせてもらいました。しかし、2003年くらいから突如として危機が訪れるようになったんです。

インターネットの普及がラジオ業界にもたらした激震
――一体何が起きたのですか?
ある日、いろんな企業から電話がかかってきて「インターネットラジオという手法を使えば、かねやんに払っている半分以下の金額でプロモーションができる」と、スポンサーが次々と降りてしまったんです。『音泉』や『ランティスウェブラジオ』といったインターネットラジオの登場でした。ラジオ大阪は文化放送との関係を活かしても関東・関西にしか放送できないし、AMだから若干の雑音も混じる。低価格で全国にクリアな音を届けられるなら、そちらに乗り換えたくもなりますよ。インターネットの普及でパッケージメディアも売れなくなっていて、どの企業もスポンサー料を払えなくなっていましたから。
その頃既に始まっていた『岩田光央・鈴村健一 スウィートイグニッション』(通称『イグニ』)は、そんなラジオ大阪の苦闘と苦心の歴史を一番知っている番組です。スタート当時はたくさんのスポンサーがついていたけれど、それが一社抜け、二社抜け、「このままでは番組を畳むしかない!」という危機的状況は何度もありました。それでも今日まで続けてこられたのは、新しいテクノロジーやビジネスモデルを取り入れて成長できたから。だから15年も続いているのだと思います。
――ニコニコチャンネルの開設や、CD・グッズの販売ですね。
「ほかの会社はグッズをつくっている。よくわからないけれどウチもつくってみるか」と。僕はジャーナリストになりたくてラジオ大阪に入ったので、どんなグッズをつくったらいいのかなんて正直わからない。でも、ラジオ局が本を出しても、CDを出しても、コミックマーケットに出展しても違和感がないのは、インターネットが業界の垣根を壊したからなんです。

――兼田さんが「かねやん」としてメディアに顔を出すようになったのも、そのような背景があったから?
それは僕が営業だから。営業はスポンサーやお金を出してくださる人に「皆さんあってのラジオ大阪、だから支えてください」とお願いするのが仕事です。営業だから顧客の声も聴くし、期待になるべく応えようと努力する。それに相手の顔がわかった方が顧客はお金を出しやすいでしょ。
普通の民間放送では、番組制作に直接関わるのはクライアントで聴衆者は制作に関わりません。でも、アニラジは好きな人がグッズを買って、メールを出すことで支えられています。聴衆者が番組の制作に関わっているんですよ。これが僕がアニラジのスキームを素敵だなと思う理由。一聴衆者と相対するなんて本当はすごく面倒なことだけれど、この関係性をつくれるアニラジは面白いと思います。
ですがそれは裏を返せば、出演声優の人気が落ちればアニラジも終わるということです。僕らは彼らの人気が落ちないように、手を変え品を変え、みんなで頑張ってきました。
――『森久保祥太郎×浪川大輔 つまみは塩だけ』(通称『つま塩』)の300回記念放送に出演された際、「この番組がこんなに続くとは思っていなかった」という趣旨の話をされていましたが、それは何故ですか?
ニュース番組はニュースを伝えることが目的。『ゆりゆららららゆるゆり放送室』や『Fate/Grand Order カルデア・ラジオ局』は作品を盛り上げることが目的。でも、『イグニ』や『つま塩』はそういった第三者からの欲求がありません。ですから複数の声優が関わる番組の場合、それぞれの声優が番組に対して同じ思いを持ってくれていることが、続けていくうえで大きな要因になります。
ぶっちゃけた話、ラジオはギャラが安いので、優先順位が低くなりがちです。それなのに毎週決まった時間を押さえる必要がある。たとえAが「ラジオのためにスケジュール押さえます」と言ってくれても、Bが「他の仕事の合間に制作してください」という方針だったら、Aはその空気を嫌でも感じます。今のゲーム業界ならお金があるから声優のスケジュールを押さえることも容易ですが、ラジオ局は違いますから、お金じゃなくて人間関係を積み重ねていかざるを得ません。だから制作サイドは番組づくりにおいて楽しい環境を提供するよう気をつけなくちゃいけないと思いますね。
『つま塩』の場合、浪川はKiramuneの活動もあるし、社長業もしている。森久保も歌手活動をしているし、最近は独立したばかり。お互い忙しいから、どこかでスケジュールに無理がくると思っていました。それなのにあの番組が今日まで続いているのは、二人があの番組のことを本当に大切にしてくれている証拠です。優先順位の低いラジオという仕事を5年も続けるというのはそうゆうことなんです。だからこそファンの方は、これからも絶対に『つま塩』を聞いてあげてください。何故なら、ほかならぬ彼らが『つま塩』を愛しているのだから。
――ラジオ業界で働くということは、良好な人間関係の構築が不可欠ということですね。
ラジオは「ショー」としてたくさんの人に見てもらうものではなく、「生活」としてリスナーとパーソナリティの両方に寄り添うものですから。
1月から始める新会社は、生活やコミュニケーションに根差した事業立脚でやっていきます。特に、声優は「エンターテイナーとしての側面」と、生活を見せる「ヒューマンとしての側面」という二つの側面を持っていた方がタレントとして大きくなれると思うので、声優のヒューマンとしての価値を高めてあげるお手伝いがしたいですね。僕にとってはリスナーも声優も等しく大切で、自分の子どもみたいな存在だからこそ、その両者が幸せになれる、小さく濃い、人間関係に基づいた「ミニマムエンターテインメント」を追求したいと考えています。

ラジオ業界、アニラジ業界で働くということ
――1月からの新会社「株式会社ベルガモ」について教えてください。
ベルガモはイタリアの都市の名前です。ベルガモという場所は、歴史上、ミラノやヴェネツィアといった大都市に挟まれ、またナポレオンに攻められながらも、独自の生き方でのらりくらりと渡り歩いてきた小都市です。小さいながら街の雰囲気も良く、僕らしくていいかなと社名に選びました。
ラジオ大阪は社名を見れば「大阪の人に喜んでもらうラジオを提供すること」という企業目的が明確で、その目的のために邁進していける良さがある反面、限界も感じていました。だから、せっかく辞めて新しいことをするなら、企業目的が明確じゃない社名にしたかったんですよ。一見しただけでは何をするかわからない会社。クリーク・アンド・リバー社と一緒ですね。
――(笑)。
ただ、やることはこれまでと一緒でアニラジを起点に発展しようと考えています。とはいっても社員は僕一人だけだから、「下請けから何からなんでもやりまっせ!」なんて言えない。これまで作ってきた人脈を頼りにコンテンツを回していくことになると思います。
――採用しようとは考えないのですか?
今後はアニラジ以外にも手を伸ばしたくなるかもしれませんから。一緒に仕事をしていく中で「この人とやりたい!」と思えたら採用するかもしれないけれど、最初は一人の予定です。
人材は難しいですよ。オタクを採用するのは特に。趣味と商売のギリギリのラインを常に追求しなきゃいけないし、好きを理由にトコトン追求して体を壊したって誰も何も評価しない。

――ラジオ業界の労働環境って実際どうなんですか?
AMラジオは放送業界の元祖。テレビができる遥か昔から存在しているから、各局とも手当てや福利厚生はすごくしっかりしています。であるが故に社員を採るのは大変で、アンポンタンを採用してしまうリスクが高いからこそ、他の業界に比べてラジオ業界はアウトソーシング化が異常に早く成長していきました。それに、ラジオ局の社員は基本的に総合職だから、会社の都合で職種が変わったり異動させられたりは当たり前。それが嫌でフリーランスになる人も多いですね。
――そういえば、アニラジの現場はほとんど外注スタッフですよね。
何故かというと、もともとアニラジはこんなに大きくなると思ってなかったから、会社でつくる枠組みの中に入っていないんですよ。それに、「声優の○○って誰?」と思いながら内製するくらいなら、知っている人を外注した方が安心でしょ。
――なるほど。そういったスタッフはどうやって集めているのですか?
ほとんどは一緒に働いている人の紹介。アルバイトは専門学校の子たち。大学を卒業して局に入る選択肢もあるけれど、それは総合職だから、専門職としてやりたいのであれば、専門学校に入ってフリーとして活動したり、制作会社に入ったりするのも手です。
――ラジオ局に入って活躍するための考え方についてお聞かせください。
ラジオ局に入りたい人は以前に比べて増えていますが、その理由はアニラジにほかなりません。ラジオ大阪や文化放送だけならまだしも、一部のFM局でも「アニラジが好きだから」という理由で応募が増えていると聞きます。そんな方々にお伝えしたいのは、自分がラジオ業界志望者なのか、アニメ業界志望者なのか、まずそれを考えてみてほしいということです。
運よくラジオ局に採用されたとしても、昼間の高年齢層向けの番組に配属される可能性もあります。それでも最初の2、3年は我慢できるだろうし、それで「あっているな」と思えたら続ければいいけれど、「ちょっと違うな」と思うなら続けるのは難しいですよ。僕の場合はアニラジが面白いなって思えたから27年間できましたけど。
――兼田さん自身、ラジオ大阪での経験を振り返ってみてどうですか?
入社当初はラジオ局に入ったからにはラジオだけをつくり続けていくものだとばかり思っていました。それなのに、CDをつくって、レコード会社の知り合いに「かねやんのところは儲かって良いですね」なんて言われる。CDをつくるのは本来、彼らの仕事なのに、そうした垣根をインターネットが壊しました。こうした変化で雇用も流動化して、数年後に別の会社でまったく違う仕事に就いている人もいます。退職を前に名刺を整理したら、同じ人の違う会社の名刺が3枚も4枚も出てきて。アニラジ業界は狭いですね(笑)。
イベント一つやるにしても、社員数36人のラジオ大阪にメイク・カメラマン・スタイリストがいるわけがありませんから、当然そうした知り合いもできました。こんな変化を間近に感じることができて、ジャーナリスティックにこの分野を見られたことは、僕にとってすごく良い経験でしたし、そんな経験をさせてくれたラジオ大阪に感謝しています。
――インターネットが業界の垣根を越えて、さまざまな世界をみせてくれたのですね。兼田さんの今後のご活躍にも期待しています!

撮影:SYN.product/インタビュー・テキスト・編集:加川 愛美(CREATIVE VILLAGE編集部)