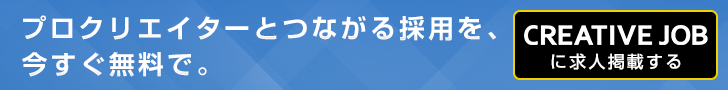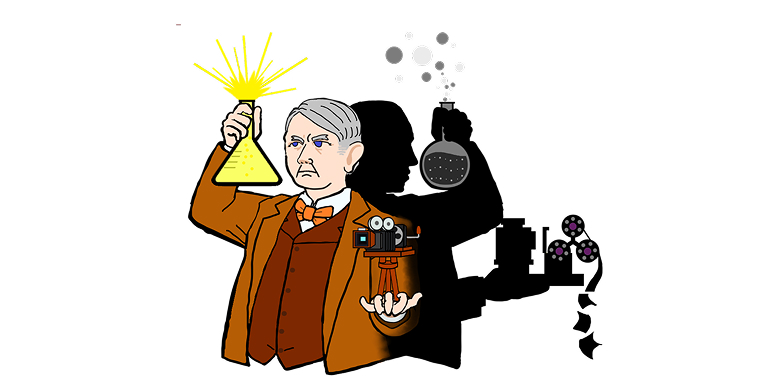その青年の母は、父を殺して無理心中した−—。カメラが追った先には、突然の母の行動を憎み、向き合おうとするも受け入れられない男性がいました。
2018年6月24日(日)にフジテレビで放送されたドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション 父を殺した母へ 〜無理心中から17年目の旅〜』は、放送直後、大きな反響を得ました。殺人者となった母の想いを辿るだけでなく、生活する日本を離れ、自らのルーツである韓国や台湾をも巡る男性。犯罪と、家族と、国籍と……さまざまな要素に押しつぶされそうになる彼を丁寧にとらえたドキュメンタリーは多くの人の心を動かし、国際的メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル」でドキュメンタリー・人物伝記部門の銅賞を受賞しました。そのディレクターである松竹英里さんに「人生を撮る」ドキュメンタリーの仕事について伺いました。
モザイクは必要最小限で
——受賞作『ザ・ノンフィクション 父を殺した母へ 〜無理心中から17年目の旅〜』は、韓国人の母が日本人の義父と無理心中を図り、ひとり残された男性・前田さんを追ったドキュメンタリーです。松竹さんはこれまでもさまざまなドキュメンタリーを撮られていますが、その動機はどこにあるのでしょう?
まず、興味がわくかどうか。これまでに、戦争経験者の方や、後に事件を起こしてしまうスポーツ選手のドキュメンタリーなどを撮影してきました。どれも「どういうことなんだろう」「この先どうなるんだろう」という現在進行形の出来事です。わからないからもっと理解したい……そう思っているので、結果的にセンシティブな題材になってしまうことが多いですね。
『父を殺した母へ』は、当時、ある事件の死刑囚の息子さんを取材していたんです。その息子さんが「親は自分で選べない」という話をしてたのが胸に引っかかっていた時期に、たまたま前田さんに出会いました。前田さんは、お母さんがお義父さんを殺して自殺した……にも関わらず、その出来事を舞台にして上演しようとしていたんです。「なんで彼はここまで行きついたんだろう?」という疑問がわき上がってきて、すぐに「撮影させてほしい」と依頼しました。
——番組になる、という確信はあったんですか?いくら撮りたくても、番組として成立しないと予算がでないと思うのですが。
いける、という思いはありました。ドキュメンタリーの撮影経験が多い方は、話を聞いて1分以内に番組として成立するかがわかる、と言われたことがあるんです。私も前田さんに会った時に「番組になる!」と直感しました。
その時期は1日も休みがないくらい忙しかったけれど、彼を撮りたいと思う人がいつ現れてもおかしくないと思ったので、その日のうちに企画書を書いたんです。読んだプロデューサーも「いいね!」と言ってくださって、撮影が動き出しました。
——しかし「無理心中」というとてもセンシティブな内容です。事件をドキュメンタリーとして放送するにあたり、どのようなことに気をつけていますか?
まず決めていたのは、モザイクは必要最小限にしてできるだけ隠さないこと。同時に、関わる人の人権をきちんと保護すること。この2つを守るのが最低条件でした。たとえば、今もご遺族がいるので、その方々のプライバシーを侵害しないように最低限のモザイクはかけ、現場が特定できるような場所は映さないようにしています。
そして、必要以上に誰かをかばわないこと。殺した人も、殺された人も、「実はこんなすごい人だったんだよ」などこちらが都合のいいように亡くなった方を印象づけることは言わずに、淡々と事実を述べることを心がけました。また、センセーショナルな事件を突きつめるのではなく、そこで生きる前田さんとお母さんや遺された親戚との関係を大事にしました。やっぱり視聴者には「人間」を見て欲しいし、自分で感じて判断することが大事だと思うんです。
「取材をやめてほしい」と何度も言われた
——ドキュメンタリーの出演者とは、どのように関係をつくっていくのでしょう?
本人の気持ちを大事にすることこと、そのためには距離をとることが大切だと、『父を殺した母へ』の取材で実感しました。撮影中に、私が前田さんに気持ちが入りすぎてしまって感情的になってしまったんです。思いが強くなって「あなたもこう思うでしょ?」と相手を引きずってしまいそうになりました。寄り添うことも大切なんですけれど、「この物語はあなたのものですよ」と一線引かないといけない。
それはドキュメンタリーを撮りはじめた時から言われたことでもあって、先輩から「壁を一枚隔てた方がいい」とよく聞かされたんです。新人の頃は、遺族が事件現場で大泣きしているのを見て私も泣いちゃったんですが、その時に「泣くな。絶対にダメだ!」と怒られました。相手が精神的に落ち込んだ時に、気持ちが入り込みすぎていたらこっちも精神がやられてしまって撮影どころじゃなくなってしまう……と。当時はその意味が分からなかったんですが、今回やっと実感しました。
——撮影を続けることが難しくなったりしませんでしたか?
4回くらい「取材をやめてほしい」と言われましたね。でもそれは私との関係というか、なぜ母が父と無理心中をはかったのかを突き詰めていく過程で、いろんな事実が明らかになっていくのが本人のストレスだったようです。だから私は「ちょっと時間を置いてみましょう」と言ったりして、時間をかけていくうちに本人の気持ちも落ち着いてまた撮影を再会して……ということを繰り返していました。
トラブルもたくさんありましたが、一番大変だったのは悪阻(つわり)かも(笑)
体調も悪いし、気分も落ち着かない。彼は韓国と台湾の血を引いているので日本に親戚はおらず、悪阻をかかえながら台湾や韓国にまで取材にも行きました。でも、旦那さんがカメラマンだったので怒りも悩みも半減されたのは助かりました。
——夫婦で取材していたんですね!仕事のパートナーはとても重要な存在だと思いますが、夫婦で取材というのはいかがですか?
善し悪しありますね。仕事でもプライベートでも一緒なので、家に帰ってもケンカになるんですよ。「あの映像おかしくない?」とか「あそこであの質問はないよね?」とものすごくケンカしました。反面、頼み事や相談はしやすいので、取材がうまくいっていない時はとてもありがたかったです。
——しかも「ニューヨーク・フェスティバル」で受賞したのが、出産の直後ですよね?
そうなんです。ちょうど出産後で、バタバタしていたので受賞の連絡をいただいていたのに気づかなくて……。返信がないのを待ちかねたプロデューサーから「メール見て!」と言われてやっと受賞に気づきました。ものすごく嬉しかったです!

——そもそも、どういう経緯で受賞に至ったんですか?
企画の段階でも「ニューヨーク・フェスティバルに選ばれたらラスベガスにタダで行けるよ」なんて言われていたんです。もちろん、その時は冗談だったんですよ(笑)私としては、夫婦で作ったドキュメンタリーなので二人の名前がテレビのエンドロールにのるだけでも嬉しかったんです。それが、いざ蓋をあけてみると高評価をいただいて「いろんな海外の賞に出してみよう」と出展したらファイナリストに残って、賞をいただくことができました。
ものすごく苦労した作品だったので、報われた気持ちでしたね。お金も時間もかかったし、夫婦ゲンカもたくさんしたし、編集の手直しもとにかく多かった。まぁ、一番つらかったのは悪阻ですけどね……。
そんな山を越えてラスベガスでの授賞式に行ったんですが、現地のディレクターに女性や年配の方が多くて「また頑張らなきゃな」と前向きな気持ちになって帰ってきました。今は育児休暇中ですが、終わったら撮りたいものがたくさんありますね!
——今後撮ってみたいものは?
被爆者、ですね。私は長崎出身の被爆三世で、夫は広島出身なので、二人で「やりたいね」と話しています。産まれた子どもは被爆四世に当たるので、なにかしらの形で残していきたい。すでに在米の被爆者の方などについてリサーチを始めています。
もともとスポーツや料理を撮りたかった
——最初から、松竹さんはドキュメンタリー監督を目指していたんですか?
いえ、初めはスポーツ番組や料理番組や情報番組をつくりたかったんです。クリーク・アンド・リバー社(C&R社)に入社したのも、大きな会社でいろんなジャンルに関わっているから、やりたいことのどれかはできるだろうと思って選びました。
入社後3年間は名古屋のテレビ局に配属になって記者をしていて、その後、東京で希望していたスポーツ番組をつくるようになりました。4年目の中頃から番組をいろいろ掛け持つようになって、今ではニュースとドキュメンタリーの特番が半々です。
だから報道をやりたかったわけではないんです。でも、先輩でフジテレビの『世紀の大事件』などの総合演出をされている加藤健太郎さんのもとでいろいろと教えていただいて、考え方が変わってきました。加藤さんの事件取材のやり方、関係者の方との向き合い方などを傍で見ていて「あんなふうに自分もできるようになれればいいな」と思うようになりました。今回の『父を殺した母へ』でも大変お世話になり、身近に人としても、仕事人としても尊敬できる方がいることは本当に恵まれていると思います。
——取材を重ねていくうちに、だんだんとドキュメンタリーの仕事に惹かれていったんですね。
ええ。実際にお会いしたご遺族の存在も大きくて、お話を聞いているうちに、「取材してこれっきりになるのはすごく寂しいな」と思うようになってきたんです。相手にとって失礼なことを質問しなきゃいけないこともあるし、そんなその場限りの取材が嫌で、一言だけでもお話を聞いた方にはお礼の手紙を出すことにしました。返事が来なくても毎月出し続けているうちに、一年以上してご遺族の方から「話を聞いてほしい」とご連絡をいただくようになりました。それからですね、ドキュメンタリーをやりたいなという気持ちになったのは。事件が話題になったその時だけ取材するんじゃなくて、その後の人生をきちんと伝えたいと思うようになりました。
——手紙を出し続けることで、ご遺族の方々のお気持ちも変わっていくんですね。
「その場限りじゃないですよ。まだ繋がっていますよ」ということは、伝えないと伝わらないですしね。手紙の内容はなんでもいいんです。雑談でもいいから1ヶ月に1度「いかがですか?」とお手紙を出し続けているうちに、自分のことも覚えてもらえるし、少しですが関係もできていく。今も1ヶ月に30通くらいは書いてます。メールよりSNSより、絶対に手書きの手紙がいいですね。手元に残るし、気持ちが伝わります。後輩にも「手紙を書いた方がいい」とはよく言っています。
——手紙以外に、ドキュメンタリーを志す人へのアドバイスや、大事にしていることはありますか?
とりあえず、思いたったら即行動!自分が「これ面白い」と気づいた時には、少なくとも5人は同じように感じていると思った方がいい。後回しにしていたら他の人に先を越されてしまう。ひとまずその日に電話をしてアポを取り付けて、自分が一番に話を聞きに行って「取材させてください」と言わないとダメです。

——ドキュメンタリー制作で、一緒に働く人に求めるものはなんですか?
とりあえず「やっていいよ」と言ってくれる人はやりやすいですね。お金や時間など事情はいろいろあるだろうけど、「これはダメ」「あれはダメ」とすぐに否定されると動けなくなってしまう。とくにテレビ局だとそれぞれ部署によって担当があって、それぞれに確認していると時間がかかります。それをまず「話だけでも聞いてくれば?」「行動してみれば?」と後押ししてくれる人がいる環境は大事ですね。
だから後輩でも、最初から「無理ですよね?」と及び腰じゃなく、「とりあえず行っていいですか?」と前のめりな姿勢だといいですね。動いてみると、意外とすんなり進むことも多いですから。
——今後の働き方について、将来フリーランスのドキュメンタリー監督になるなど展望はありますか?
今すでに制作会社(C&R社)に所属しながらフリーランスのような勤務形態なので、働きやすいですね。取材先も自分から提案して、自分でアポをとっているので、内容も勤務時間も調整できます。体調が悪くなったら自分でやすめるので、妊娠中や子育て中でも働きやすいですね。
なにより、C&R社は会社が大きくてプロデューサーも何人もいるので、企画を出したら誰か一人くらいは興味を持ってもらえることが多いです。やりたいことがやれる環境にいるので、このまま働き続けて、多くの方々に届く番組をつくりたいです。
インタビュー・テキスト:河野 桃子/撮影:ヒロヤス・カイ/編集:CREATIVE VILLAGE編集部
番組紹介
フジテレビ系列『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00~)
公式サイト
http://www.fujitv.co.jp/thenonfx/