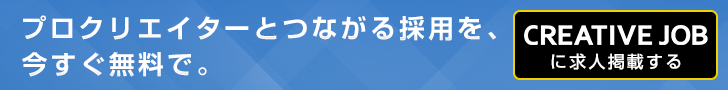物語構成やワンシーン・ワンカットの撮影といった「体験する映画」に興奮した観客の口コミから大ヒットに繋がった『カメラを止めるな!』(2017)。
今回はDVDリリースに加え、第42回 日本アカデミー賞 最優秀編集賞を受賞した映画監督・上田慎一郎さんにインタビュー。
奥様・ふくだみゆきさんをはじめとした人々と作品の関係について伺いました。
1984年 滋賀県出身。中学生の頃から自主映画を制作し、高校卒業後も独学で映画を学ぶ。2010年、映画製作団体PANPOKOPINAを結成。現在までに8本の映画を監督し、国内外の映画祭で20のグランプリを含む46冠を獲得。
2015年、オムニバス映画「4/猫」の1編「猫まんま」の監督で商業デビュー。妻であるふくだみゆきの監督作「こんぷれっくす×コンプレックス」(2015年)、「耳かきランデブー」(2017年)等ではプロデューサーも務めている。「100年後に観てもおもしろい映画」をスローガンに娯楽性の高いエンターテイメント作品を創り続けている。『カメラを止めるな!』(2017)が劇場用長編デビュー作となる。
カメラを止められなかった自分と…
――上京後ホームレスになるなど、壮絶なクリエイター人生を歩まれた中で奥様・ふくだみゆきさんの存在がご自身をさらに挑戦的にしたそうですね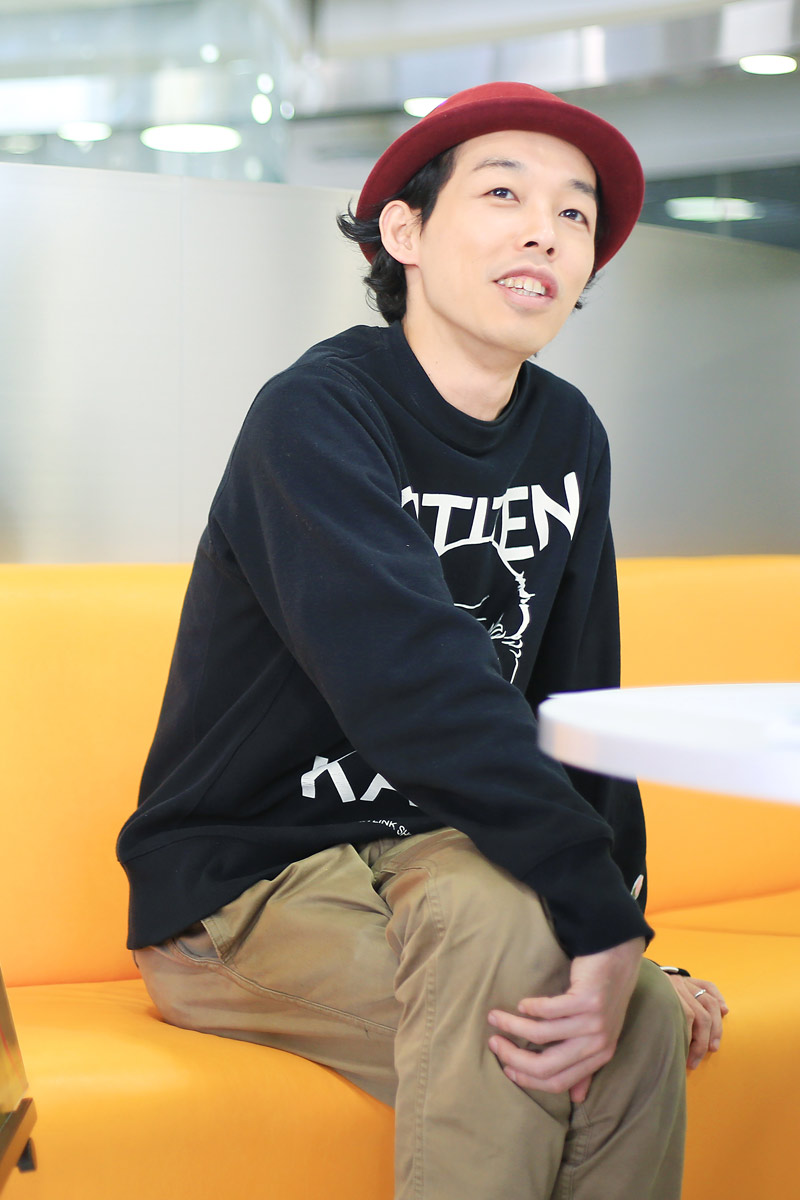
「挑戦的」といっても、向こう見ずな状態で挑戦を続けていたら洒落にならないんですよね。笑
25歳までの自分が良い例でとにかく「クリエイターになる」という目標に挑戦的すぎて、地に足がついていなかったんです。
つまり、クリエイターが挑戦的になるためには、現実とのバランスを取る必要がある
。
上映館数2館から始まった『カメラを止めるな!』が300館以上 で上映され、このようにDVD化まで行きつけた僕の場合は特に妻がバランサーになってくれていたと思います。
――カリスマ的イメージが強かったので、意外です
いやいや!脚本を書く段階では妻やENBUゼミナール講師でもある、映画プロデューサー・監督の榎本憲男 さん、編集の段階では映画業界ではない友達に見てもらったりして、凄く頼りながらつくったのが『カメラを止めるな!』でした。
フィードバックを活かした『カメラを止めるな!』の制作から、奇譚のない意見を言ってくれる存在がクリエイティブに大きな影響を与えることを感じましたね。
――奥様の意見は作品にどのような影響を与えましたか?
例えば、妻に出会うまで女性の描写にリアリティがなかったんです。男性が描く勝手な女性像でした。
それを妻にチェックしてもらえるようになって、リアリティのある女性が描けるようになったと思います。
妻が「女性はこの時こんなこと言わないよ」とか、「こんなシュチュエーションでこんな服を着ていかないよ」といった女性的な視点で意見をくれたおかげだと思います。
でも、自分の作品を他の人に見てもらうって怖いんですよね。
あわせて読みたい

――きっと、多くのクリエイターの悩みですね
さらに、映像や脚本をずっと編集していると客観性を失ってくるんですよ。
――というのは?
クリエイターとして作品に寄りすぎて、観客にとって面白いか否か、分からなくなってくるんです。
なので、僕は編集映像の段階でDVDに焼いて、観客に近い立場の方に作品のフィードバックをもらうようにしています。
――『カメラを止めるな!』では奥様や榎本さん以外にもフィードバックをもらっていたのですね
そうですね。妻は編集映像に意見を言うのには向いていないんですよ。制作段階を間近で見ているので、観客とクリエイターだったら、圧倒的に後者になってしまうんです。
未完成の作品を制作背景を知らない、観客に近い立場の方に見せて、さらにその反応を受け取るのは怖いです。
でも、「面白くない映画」が出来上がってしまうことの方よっぽどが怖いじゃないですか。
――フィードバックを受けとる勇気をもたないと、独りよがりで「面白くない映画」になってしまう…と
そうですね。これは人生も同じだと思います。作品以外でも、日常生活の行動で妻に意見をもらうことがありますから。
『カメラを止めるな!』の脚本を見せているのと同じように、僕の人生の脚本も妻がチェックしているようなイメージですね。(笑)

自分の作品がチェックされることはあっても、妻と出会うまでは自分の人生をチェックする人はいませんでした。なので、「前のめり」の程度が分からずに、「痛い思い」をすることになるのですが…。
――「痛い思い」というのは上京されてからのご経験についてでしょうか?
そうですね。借金を背負い、ホームレスになったり…ただ、それもそれで痛くて良かったな、と思いますけどね。ぜんぶ『カメラを止めるな!』に活きているので。
岡本太郎の言葉との出会い
――「制約を作品に活かす」きっかっけになったクリエイティブはありますか?
本や映画をシャワーのように浴びているうちにどこかでそうなったんでしょうね。
何か1つあげられた方がキャッチ―だと思うのですが…クリエイティブに行きつく過程はそんなに簡単じゃないと思うんです。
あわせて読みたい
強いて言うなら、岡本太郎さんが著書で語っている言葉が自分の人生をなぞっているようで、最初に読んだときは涙がでるくらい感銘を受けました。
1度目の上京をした、20歳くらいのときだと思います。上京後に遭遇した困難と繋がったんです。
特に印象に残っているのはこの言葉です。
「いいかい、怖かったら怖いほど、逆にそこに飛び込むんだ」
※出典『強く生きる言葉 』(2003/イーストプレス)
――2つ目の言葉は編集映像を見せることが「怖い」けれどもそれを活かして『カメラを止めるな!』をつくられた上田さんの姿に重なりますね
あとは、元々困難や不可能だと思われることに立ち向かうことに面白みを感じる素質もあったと思います。
――企業に入社してクリエイターを目指す、というレールには乗らない生き方を選ばれたのも「素質」からなのでしょうか?
そうかもしれないですね。ただ、脱線という概念をつくるにはレールが必要なんです。脚本通りに人生を進んでいくというよりは、この取材でもそうですが、その時に起きたことからしゃべって、リアクション受けて生まれてくるものをクリエイティブと言いたいです。
つまり、「レールがあった上で」脱線した部分に面白いものがあると僕は思うんです。
ちなみに、妻もそんなにレールの上を走っている人間ではないんですよ。生き方的には自分よりレールの上を走っていると思いますが。笑
ただ、妻は自分の生き方にも、クリエイティブにもツッコミを入れてくれる貴重な存在です。
制約があるからクリエイティブを生み出せる
なので、自分の作品は限られた時間・空間の中でつくられたものが多いです。でも、これは決してマイナスにはならないと思うんですよ。
「なんでも好きなことやって」と言われても、アイディアは浮かびづらい。「20代の若者をテーマに青春ものを」みたいに、お題を与えてもらった方がアイディアは浮かびやすいんですよね。
加えて僕の場合は、台本を練り込んで、リハーサルを重ねて作品づくりを進めていきます。
でも、いざ現場で撮る時は余裕がない状況をあえてつくって「どう壊せるか」つまり「台本(レール)から外れてくれないかな」と思いながら撮っているんです。映像を編集しているときも、台本通りじゃない繋ぎ方でつないだらどうかな、と常にドキュメントを取り込むことを意識しています。
――大勢のクリエイターが関わる映像制作の現場では難しそうですね
そうですね。さらにわざと台本(レール)から外れたら意味がないんです。
難易度が高すぎるものをつくろうとしたら、必ず破綻してしまうじゃないですか。
なので、背伸びして届くかどうかギリギリの負荷を設定することを作品づくりの度に意識していますね。
作家性はにじみ出てくるもの
――松竹ブロードキャスティングさんとの新作プロジェクトは「作家主義」がテーマの1つのようですが、ご自身の作家性についてどのようにお考えですか?
作家性は意識していません。例えば「僕の作家性は役者を活かすこと」と決めたとしたら、その言葉に囚われて、どの作品でも役者を活かそうと意識してしまう。
つまり、決めた作家性に囚われて本当の作家性がなくなるんですよ。『カメラを止めるな!』の劇中でも言っていることですが、クリエイターの作家性は「出すんじゃなくて出るんだよ!」だと思うんです。

――『カメラを止めるな!』もテーマを決めずにつくられたそうですね
そうですね。強固なメッセージやテーマから生まれる作品があっても良いと思うのですが、特に自分は必死に生きて、作品をつくっている中で「にじみ出てくるもの」をクリエイティブに変えているのだと思いますね。
――特に若手の映像クリエイターはテーマを決めて作品をつくることが多いと思いますが
そうですね。でも、「自分らしいクリエイティブ」を決めてしまったら苦しくなると思うんです。
そのテーマから外れたとき、本当に自分のクリエイティブなのか迷うじゃないですか。なので、それを一旦忘れて、毎日を夢中で生きていた方がよっぽど自分らしい、唯一無二のクリエイティブに通じると思うんです。
そうだ…この間、若手クリエイターに向けたメッセージで「クリエイターとは何でしょうか?」と聞かれたんですよ。その時、僕は「人間だ」と答えました。
――「人生からにじみ出るメッセージ」つまり、個人の生き様が上田監督の考える作家性ということですね
『カメラを止めるな!』の前、短編映画を7本ほどつくっていた時期は「自分らしい映画をつくろう」と作家性を捻出していました。
一方、『カメラを止めるな!』は必死に制作するなかでクリエイティビティがにじみ出た作品です。つまり、過去作とは逆に作家性の純度が高い作品だと考えています。
僕もこの考えに行きつくのに時間がかかりましたが、『カメラを止めるな!』を皆さんに観ていただけたことで、「作家性はにじみ出るもの」という考えに確信をもつことができました。

――周りの人々にカメラを「止めて」もらいながら監督を務めた『カメラを止めるな!』。
その制作過程からにじみ出たものが作家性に繋がった、ということですね。本日はありがとうございました!
撮影:TAKASHI KISHINAMI/企画・インタビュー・テキスト:大沢愛(CREATIVE VILLAGE編集部)
クリーク・アンド・リバー社の転職支援サービス
あなたのクリエイティブを最大限に活かすために、クリエイティブ業界に精通したエージェントが転職をサポートさせていただきます。
【無料】就業支援サービス