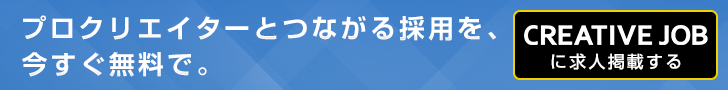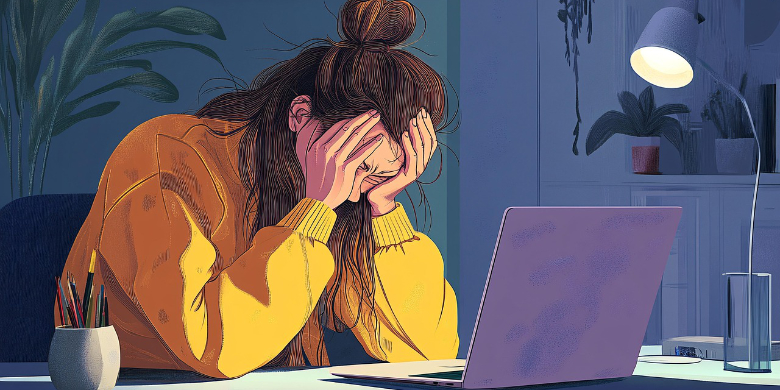――芸術の世界で生きる喜びと苦しみを描き絶賛を集めるマンガ『ブルーピリオド』。実写映画化を手がけた監督・萩原健太郎にとって、絵を描くことに生きる意味を見出し、がむしゃらに向かっていく主人公・八虎(やとら)はかつての自分そのものだった。大事にしたのは原作におもねらないこと。「マンガ『ブルーピリオド』の面白さって言葉の力でもあると思うのですが、それをいかに映像で語るか。原作者の山口先生は、何を取捨選択しどう描くかという現場の判断を尊重し、信頼して託してくださった。本当にありがたかったです」。“好き”に出会い、人生を賭ける人間が共鳴し合いつくりあげた映画「ブルービリオド」には、自身を生きたいと願う人へのエールがつまっている。――
どうしても本当の渋谷で撮りたかった
マンガ『ブルーピリオド』の実写映画化のお話をいただいたのは2020年の夏だったと思います。僕が監督した映画「サヨナラまでの30分」(20)を観て依頼してくださったようです。僕は作者の山口つばさ先生の、正解もゴールもわかりにくい芸術をスポ根ものとして明快に表現するというコンセプトが好きで、それで、ワーナー ブラザース映画さんとC&Iエンタテインメントさんと僕とで企画書とイメージプランをまとめ、出版元の講談社さんにプレゼンしました。当初のアイデアではCGをゴリゴリに使う予定でした。絵を描くという行為は動きがとてもミニマムなので実は映画的ではないということもあって、描いている主人公・八虎の脳内をCGを駆使して躍動的に見せるという演出プランを提案しました。それが評価されたのですが、最終的に仕上がった映画はそこからかなり変わっています。というのも、絵を描くってすごくアナログな行為だから、CGとの食い合わせが悪い気がして、それで、いかにアナログ感を出すかということを考えるようになりました。例えば、原作にもある八虎が渋谷に浮くシーンも、最近は栃木の足利スクランブルシティスタジオに渋谷のスクランブル交差点のセットがあるので、そこで撮ってCGでビルを合成したりするのですが、僕はどうしても本当の渋谷で撮りたいと思いました。

それで約1年かけて制作部が粘り強く交渉してくださって、SHIBUYA109の前で撮影が実現しました。夜中にクレーンを入れて、本当は八虎役の(眞栄田)郷敦も一緒に吊ろうと思っていたのですが(笑)、クレーンを2台置くのはさすがに無理ってことで、郷敦だけ合成しました。郷敦に寄ったカメラが回転して渋谷の街が映るところに、走ってきた自転車が映り込んできて、本来なら消しちゃうところですが、もったいないなと思って。CGだったら余計なコストがかかるので通りがかりの自転車なんて絶対につくらないだろうし、チラッと鳥が飛んでいたりするのもそのままにしています。撮影時のリアルな感覚、いかにアナログの手触り感を残すかということを大事に考えていました。
眞栄田郷敦は努力の人です
八虎のキャスティングはかなり難航しました。紆余曲折の末に郷敦の名前があがったのですが、郷敦とは以前、関西テレビの2時間ドラマ「あと3回、君に会える」(20)を一緒にやっていて、そのときはちょっと存在感が薄く、真面目な子だなって印象しかなかった。だから本当に主演でやれるのかって若干不安でした。でも、ドラマ「エルピス —希望、あるいは災い—」(22、関西テレビ)でブレークスルーした感もあったし、郷敦が以前インタビューで、また僕と一緒に仕事したいと言ってくれていたのも知っていました。そういう関係性もあったから、郷敦も八虎役を受けてくれたんだと思います。

ユカちゃんこと鮎川龍二役も悩みました。ユカちゃんは女装男子で原作だと女の子に間違われるぐらいフェミニンなわけだから、男性キャストでいいのか、女性のほうがいいのか、それとも本物の女装男子にお願いするのはどうかと試行錯誤していると、プロデューサーが高橋文哉くんの名前をあげてくれました。とても綺麗な顔立ちなのに芯の強さがあって、文哉くんなら映画ならではのユカちゃんがつくれると思いました。世田介は板垣李光人くんしかいないなと。ご本人も絵を描いていますしね。森まる役も桜田ひよりちゃんしか思い浮かびませんでした。郷敦と八虎の共通している部分は、決めたことはとことんやり抜く集中力とストイックさです。あと、郷敦も天才というより努力の人なんですよ。そこも似ています。その点は、文哉くんも、板垣くんも、ひよりちゃんも同じです。4人ともめちゃくちゃ努力家です。郷敦は撮影の合間にもずっと絵を描いていて、そういう姿に全員が刺激を受けましたし、キャストもスタッフもだれひとり妥協しない、本当にストイックな現場でした。撮影期間は、2023年6月半ばから7月にかけての約1か月間だったのですが、真冬の設定なので厚着をしてエアコンもない中で撮るという、あれもなかなかストイックでした(笑)。

圧巻だった水族館での撮影
今回一番気をつけたのは、「原作に囚われすぎない」ということです。原作がこうだからって思考に陥っちゃうと、なんのための実写映画化かわからないし、それってある意味こちら側のクリエイティブを放棄していることにもなりかねない。例えば、八虎と世田介の関係性って映画ではあまり触れられてないんです。そうする八虎と世田介のやり取りの場面で八虎役の郷敦が、「いや、これ言えないっすよ。だって嫌いですもん、この人(世田介)」って言う。「確かにそうだな。こんなこと言われて、相手を好きでいられるわけないよな」って僕も思って、じゃあ、こういうふうなことなら言えるのかな?とかって、原作から離れすぎず、かつ映画独自のものを大切にという微妙な感情のチューニングが必要でした。マンガ原作を実写化する上で、とても重要な作業だったと思います。

撮影で印象深かったのは、ユカちゃんが佐々木くんに振られて、水族館で八虎とふたりで話すシーンです。本当はもっといろんなカットを撮る予定で、まずふたりのバックショットからと思って撮ったらそれがめちゃくちゃよくて。魚も芝居に合わせていい感じで動いてくれて、これはもう!っていう抜群の出来で、そのワンカットで終了にしました。原作ではボロボロ泣いているユカちゃんが印象的なシーンだし、リハの文哉くんの芝居もとてもよかったんだけど、「原作がこうだから」ってなっちゃうのはやっぱり違うと思ってましたから。絵と映画の大きな違いは、能動的に見るか見ないかで、映画ってどんどん流れていくので受け身でいれちゃうところがある。でも今回は、絵を見るような映画にしたかった。ワンカットの画(え)で観ている人の想像力や感情をどれほど呼び起こせるか。文哉くんの背中と声の芝居だけでユカちゃんの哀しみや辛さや悔しさが痛いほど伝わる。とても印象的な場面になっていると思います。
一緒にやりたい人は、自分なりの哲学をちゃんと持っている
美術の宮守由衣さん、照明の平山達弥くん、撮影の光岡兵庫くんはじめスタッフにも恵まれました。光岡くんは初の劇場映画だったと思いますが、すごいです、伸び代が。僕が一緒に仕事をしたいと思うのは、仕事に対しても、生き方にも、自分なりの哲学をちゃんと持っている人です。そういう人とは同じテーブルで話し合えるんです。みんな仕事が好きだし、1ミリも手を抜かない。僕が「こうやりたい」と言っても、本当にダメなときはダメだって言いますし、「えっ、それダサいですよ」って(笑)。

本作では、マンガ原作を実写化する上で、改めていろいろな気づきやチャレンジがありました。映画的カタルシスを持たせるには、大学入試2次試験最終日の午後に八虎が課題のあの絵を描ききることにどんな意味を見出せるかが重要でした。そこをきちんと見せることができれば、きっとすごくエモーショナルになる、そういった視点で新たにドラマを組み立てていきました。芸術は情熱か、才能か。原作、そして映画にも共通する問いですが、一流の芸術家になるためにはやはり才能が必要だと思います。情熱だけではどうにもならない次元ってある。だから今回も悩みました、嘘はつきたくないので。でも大学受験なら努力で突破することができると思いました。最後に藝大入試に挑むために映画の中で八虎が描いたであろう全部の絵を出しました。その八虎の、郷敦の情熱と努力の軌跡をぜひ感じてほしいと思います。

一度は映画産業のトップをこの目で見たかった
生まれは東京で、小中高と成城学園に通っていました。勉強はできなかったし、したいとも思いませんでした。中学時代はサッカー部でしたがすぐに辞めちゃって、劇団ひまわりに入ってエキストラをやったりしていました。高校時代はグランドホッケー部でしたがゆるい感じの部活で、僕は放課後、映画館に行ったりしていました。叔父が映画の配給をやっていたので、子供の頃から映画には興味がありました。よく観ていたのはアメリカ映画で、最初に観たのは「ビートルジュース」(88)だと思います。なんか観ちゃいけないものを観ちゃったような感じでした(笑)。あと、父親が「ポリスアカデミー」(84ほか)のシリーズが大好きでよく一緒に観ていました。日本映画はほぼ観てなくて、最初に観た日本映画は「ハチ公物語」(87)だと思います。映画館ですごく泣いた記憶があります。映画も好きでしたが、映画館という特別な空間が好きでした。

高校卒業後は映像の専門学校に進み、それからアメリカに留学しました。ずっとアメリカに行きたかったんです。というのも、僕はいとこが22人いて、その中の6人がアメリカ人なんです。母親が8人きょうだいで、そのうちふたりがアメリカ人と結婚したので。夏休みになると、アメリカからそのいとこたちがよく日本に来て一緒に遊んでいました。だから、ずっとアメリカには親近感があったし、一度は映画産業のトップをこの目で見たくて、英語はほぼ話せなかったので猛勉強して、専門学校卒業後にロサンゼルスにあるアート・センター・カレッジ・オブ・デザインに入学しました。アメリカには約7年間いました。アート・センター卒業後は、AFI Conservatoryの大学院に行くか、日本に戻って仕事をするかで悩みました。アート・センターは、映画はもちろんですがコマーシャルフィルムにも強い美大で、学んでいく中でCMの面白さに目覚め、いろんなことを試し経験してから、映画の道に進むのもいいなと考えるようになりました。それで日本でCM制作ができるところを調べ、THE DIRECTORS GUILDという映像ディレクターのエージェンシーを見つけました。作品集を送ったら会っていただけることになり、参加を決め帰国しました。
どうすれば映像の世界で生きていけるのかをひたすら考えていた
1年ぐらい師匠の先輩ディレクターのCM現場に弟子としてついて、それから師匠のもとで、絵コンテを描くと3000円、企画がクライアントのところまで行くと1万円、プレゼンに通ると10万円みたいな感じでギャラも出るようになりました。でも絵も下手だったしなかなか企画も通らなくて、作業が押して深夜にタクシーで帰宅して逆にマイナスみたいな(笑)。だけど、無理だとか、やめようと思ったことは一度もありませんでした。だって、ほかの道なんてないんですもん。勉強も運動も得意じゃなかったし、自分に何ができるんだろうとずっと思っていました。それが、アメリカで最初にショートフィルムを撮ったときに、絵に出会った八虎じゃないけど、初めて生きているという実感が持てたんです。もうこれしかないと思っていたので、どう映像の世界で生きていくかということをひたすら考えていました。転機となったのは、「北陸新幹線/Friend-Ship Project ~親子のバトン~」(15)だと思います。「手をつなごう Friend-Ship Project」というプロジェクトの第12弾で、ドラマ仕立てのCMなのですが、電通の澤本嘉光さん(CMプランナー/クリエイティブ・ディレクター)が企画を手がけてらっしゃって、これはチャンスだと思いました。それで撮影を今村圭佑くんにお願いしました。今村くんはカメラマンデビューして間もない頃でしたが、彼の撮った藤井道人くんの映画「幻肢」(14)がとてもよかったんです。今村くんの天才的な画(え)も含め澤本さんがすごく評価してくれて、そこからソフトバンクやトヨタのCMの仕事につながっていきました。

これまでで一番苦しんだのは、映画「東京喰種 トーキョーグール」(17)をやっていたときです。僕の劇場初監督作品ですが、とにかく必死にやったというだけで、思うような映像表現もできなかったし、もう二度と映画はやらないかも……と思ったほどでした。お話をいただいたのがクランクインの3カ月前で、初めてのことで何もわからないまま、「やります! やりたいです!」ってプレゼンし撮れることになったのですが、時間的にも自分の実力的にも、なかなか納得のいくようなかたちでやりきることができませんでした。でも、「東京喰種」での経験が「ブルーピリオド」に活きていますし、それに、映画を観た方からお手紙をいただいたんです。中学生のお子さんを持つお母さんからで、不登校だった子供が「東京喰種」を観て自分も頑張りたいと引きこもりをやめ、高校受験にも合格したというお礼の手紙でした。苦しみながらではありましたが、自分のつくった映画がだれかの力になっている。本当にうれしかったし、いまでも僕の力にもなっています。
やりたいことがあるのなら、とにかく動くしかない
芸術は才能か、情熱か。それは僕たちクリエイターにも通じる問いだと思います。「映画業界に入りたい。どうすればいいですか?」と若い人に聞かれることがあって、これは情熱とつながるのかもしれませんが、僕は、他人(ひと)がやってないことをやることが大事だと思っています。CMをやっていたときは、どうしたら相手の需要に自分がはまるかを考えたアプローチで、作品をつくってはクリエイティブ関係者に送りまくっていました。いろんなタイプのCM演出家がいる中で、自分のどんな武器を、どう強くしていけば秀でることができるか。考えた結果、ドラマ性と映像のクオリティ、このふたつを磨いていこうと決め、実際にそれを続けていくことで、仕事をいただけるようになっていきました。

同じように映画界でも、優秀な監督さんがたくさんいる中で、どうすれば自分に仕事が来るか、自分の企画で撮れるようになるのかを考えたときに、やっぱりみんなと同じことをやっていたのでは道は開けないと思います。やりたいことがあるのなら待ってないで、とにかく動くしかない。能動的にガンガンプレゼンしていく、アメリカ人のように、頼まれてもいないのにです(笑)。だから「東京喰種」のときも自分で演出プランをつくってプレゼンしましたし、「ブルーピリオド」も当然プレゼンから参加しました。プレゼンの勝率、僕はけっこう高いんです。たぶんほかの日本の監督はやらないだろうなってことを考えながら臨んでいるからだと思います。いまやっと、映画監督としてちゃんとスタートラインに立てた、しかも1作ごとに目の前の道がどんどん広がっているような、そんな気がしているんです。
成績優秀で周りの空気を読みながらソツなく生きてきた高校生・矢口八虎(眞栄田郷敦)。美術の授業で出された課題「私の好きな風景」に、仲間と夜通し遊んだあとに迎える「明け方の青い渋谷」を描く。絵を通じて初めて本当の自分をさらけ出せたような気がした八虎は美術に興味を持ちはじめのめりこんでいく。そして、国内最難関といわれる東京藝術大学の受験を決意する。





原作:山口つばさ『ブルーピリオド』(講談社「月刊アフタヌーン」連載)
出演:眞栄田郷敦、高橋文哉、板垣李光人、桜田ひより、中島セナ、秋谷郁甫、兵頭功海、三浦誠己、やす(ずん)、石田ひかり、江口のりこ、薬師丸ひろ子
脚本:吉田玲子、音楽:小島裕規“Yaffle”
エグゼクティブプロデューサー:関口大輔、プロデューサー:豊福陽子・近藤多聞、撮影:光岡兵庫、照明:平山達弥、録音:渡辺寛志、美術:宮守由衣、編集:平井健一、助監督:山下久義、監督助手:山口和真、スタイリスト:Remi Takenouchi、ヘアメイクディレクション:古久保英人、絵画指導:海老澤功、美術アドバイザー:川田龍
製作:映画「ブルーピリオド」製作委員会、制作プロダクション:C&I エンタテインメント、配給:ワーナー・ブラザース映画
Ⓒ山口つばさ/講談社 Ⓒ2024 映画「ブルーピリオド」製作委員会
8月9日(金)全国ロードショー
インタビュー・テキスト:永瀬由佳