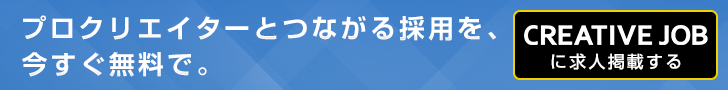2018年の連載開始以来、累計発行部数215万部を超える二宮正明が放つ衝撃のサスペンスコミック『ガンニバル』が実写ドラマ化。ディズニープラス「スター」にて独占配信中だ。狂気の世界へと誘われて行く主人公の警察官・阿川大悟役を柳楽優弥が務め、 供花村を支配する後藤家次期当主・後藤恵介役を笠松将、大悟の妻・阿川有希(ゆうき)を吉岡里帆が演じるなど、豪華演技派俳優陣が脇を固める。
監督は、『岬の兄妹』、『さがす』が国内外で絶賛された片山慎三。本作を作り上げるまでの過程やこだわり、さらに映画監督を目指したきっかけや大事にしていることを聞いた。
怖がりな人ほど、怖い作品を作ることに向いている
――まずは、原作の『ガンニバル』を初めて読んだ時の感想を教えください。
「映像化しませんか?」という話をいただいてから原作を読み始めました。最初は怖そうだな、怖いの苦手だな…と思っていたのですが、読んでいくと、どんどんハマっていって。登場人物たちの過去が明かされていく過程がとても濃いお話で。ぜひ映像化させていただきたいと思いました。
――監督は、怖いものが苦手なのですね。
苦手です。怖がりで…。でも、こういう話をすると「怖いものが苦手な人ほど、怖い作品を作ることに向いている」と言われます。怖がりな人ほど、何が怖いのかポイントを知っていると。

――映像化にあたって、たくさん準備が必要な作品だったのではないでしょうか。
そうですね。車がぶつかったり、熊が出てきたり、派手なシーンもたくさんあるので、最初は「お金がかかりそうだな」と思いました。でも、そこをちゃんと描けたら、これまでに観たことのないドラマができるなと。チャレンジのしがいのある原作だなと思いました。「人口300人にも満たない村」という原作の設定を再現するために、ロケ地には隔絶された地形で住民が村の外に出ることがほとんど無いような場所を探しました。いろいろな村を見てまわって、「森はここ」、「家はここ」というように、それぞれをチョイスして撮影をしました。小さい村の話なのですが、兵庫県、三重県、長野県で撮影をしたので、撮影規模はかなり大きいものになりました。
ドローン撮影のために、スタッフ陣で山登りを敢行
――予告編にも映っていますが、ドローンで上空から森を映したカットが印象的でした。どのようにして撮影したのでしょうか?
日本は自然が綺麗なので、森や川をしっかり見せたいという気持ちはありました。あそこは、三重県の「木津呂集落」という場所なのですが、ドローンは飛ばせる高度が決まっているので、一定以上高く飛ばしてしまうと法律違反になってしまうんですよ。なので、高い所から撮影をするには山に登る必要があって…。実際に僕とカメラマン、ドローンのオペレーターの方と機材を担いで山に登ったので大変でした(笑)。体力勝負でしたね。でも楽しかったです。
――YouTube上でも公開されている冒頭シーンでは、大悟の前任である駐在・狩野が戦慄と狂気が渦巻く村で、正気を失っていくさまが映し出されていますね。このシーンの迫力は凄まじかったです。
ファーストカットをワンカット長回しで撮る作品は多いと思うのですが、より印象的なワンカットにしたいと思いました。クレーンを2台置いて途中で(カメラを)手渡しして、という流れで撮りました。かなり大掛かりな撮影で、一日中あのシーンを撮影していましたね。狩野役を演じた矢柴俊博さんも、前のめりに何度もお芝居してくださって、最後には声が枯れるほどだったのですが、そのおかげもあって、「これから何を見せられるんだ?」という緊迫感のあるシーンが撮れたと思います。
――京介が「顔を喰われた」ことを告白する瞬間も緊張感がありますね。
手元とか、顔以外の部分も映していくのではなくて、顔をはっきりと見せたかったという思いがあります。怖いシーンを撮ることができて満足しています。

(c) 2023 Disney
リアルな表情で魅せる、柳楽優弥の凄さ

――キャスティングについても教えてください。大悟役は最初から柳楽優弥さんをイメージしていたのでしょうか?
コミックを読んでいる時から、柳楽さんしか頭に浮かばなかったですね。これまで柳楽さんが出演されてきた作品を観ていて、暴力性のあるシーンをリアルな表情で演じられる俳優さんだなと思っていたので。『ガンニバル』でも人を殴るシーンで、自然と笑顔になってるんですよね。「笑って」とお願いしたわけではないし、本人も笑っているつもりはないと思うのですが、笑顔に見える。そこがすごくリアリティに繋がっていて面白かったです。

(c) 2023 Disney
――大悟の妻・有希役を演じているのは吉岡里帆さんです。
今までやられてきた役と少し違うというか、原作の有希は時々ヤンキー口調になったりすることもある母親で、そういう所もちゃんとドラマで描きたいと思いました。吉岡さんは『泣く子はいねぇが』(2020)で、ちょっとキツイ言葉を吐くキャラクターを演じていらっしゃったので、お願いしたいなと思いました。子供にイライラしてちょっと八つ当たりしちゃったり。現実世界でもそういうことってあるじゃないですか。吉岡さんが演じることによって、リアリティはあるのだけど、観ていて嫌じゃない。そんなバランスが素晴らしかったと思います。

(c) 2023 Disney
――キャスティングで、いちばん苦労された役柄はいらっしゃいますか?
岩男です。最後の方まで決まらなくて。実際に背が高くて強そうという部分がまず大事で、何を考えているか分からない雰囲気を持っているという。いろいろと模索して、吉原光夫さんにお願いをしました。吉原さんは、こちらの要求にも細かく応えてくださって助かりました。「あまり目を見せたくない」、「口で呼吸してください」と言ったことを、ずっと守ってくれて。ヒゲも口の中に入るくらい生やしてくださって。普段の生活で邪魔だったと思うのですが、本当に助かりました。

(c) 2023 Disney
「時間をかけたからこそ良いものを作らなければ」プレッシャーも

――今回、「ディズニープラス」スター独占配信だからこそ、できたことはありましたか?
「 CGやアクションにしっかりお金をかけられるな」ということは、すごく嬉しかったです。「ディズニープラス」で人喰い村の話をやるの?と最初は驚いたのですが、怖い部分は残しつつ、ちゃんとエンターテイメントであり人間ドラマにしたいという気持ちが強かったです。民放のドラマなどに比べて、時間をかけて撮影することもできました。逆に、時間をかけたからには、それだけのものを作りたいというプレッシャーもありました。ドラマなので「続きが気になる」という仕掛けも大事になってきます。脚本の段階で話数は区切っていました。そういう部分を撮影に入る前に入念に打ち合わせしていたので、困ることはありませんでした。
――撮影前にしっかり脚本ができあがっていたからこそ展開を練ることができたのですね。
配信ドラマだからこそなのかもしれませんが、2話、3話分くらいの脚本が完成していないと、企画自体のGOサインが出ないんですよね。「この原作でいきます」というだけでは許可がおりないので、「こういうドラマになります」というルックを作る必要がありました。ましろ役はまだ決まっていなかったので、同世代の子役の女の子を見つけて森の中で撮影したり、猟銃をつきつける恵介っぽい男の人を撮影したり、イメージに合うカットをいくつか撮影して、ディズニープラスの本国に提出して。脚本の途中に撮影したカットを入れ込んでドラマの中身がイメージしやすいようにしたり、普段のドラマにはないくらい、しっかりとした企画書を用意しました。

ティザーポスターの噛み後のある腕の写真は、企画書用に撮った写真のアングルを利用しています。企画書用では、実際に噛んでもらった腕の写真を使っていて、実際のポスターの写真は造形部が作ったものではあるのですが。たくさん時間をかけて作っていますし、それを感じてもらえる作品になっていると思います。
囚われず、自由に映画を撮るということ

――監督が映画監督を志したきっかけについても、教えてください。
中学生くらいから映画が好きで、漠然と映画の道に進みたいと思っていました。漫画も好きで、漫画家にもなりたかったのですが、絵があまり上手くないので、集団でできる映画がやりたいなと。とはいえ、何からすれば良いのか分からない状態で。高校を卒業して進路を考えていく中で、お金を貯めて1年間映像塾に通って、そこにいる監督のツテでプロの現場に入り、助監督を十数年経験しました。
監督デビューするきっかけも色々といただいていたのですが、最終的には自分で作品を撮った方が良いなと思い、『岬の兄妹』(2019)を自分でお金を出して、仲間を集めて作りました。(作品作りを依頼する)逆の立場で考えたら、「何を撮るのか分からない」人には仕事を頼めないじゃないですか。そういう意味で、「僕はこういう映画を撮ります」という名刺代わりに作ったのが『岬の兄妹』です。
――影響を受けた監督や作品はありますか?
中高生の頃は、リュック・ベッソンとか、デヴィット・フィンチャーなどハリウッド映画をよく観ていました。マーティン・スコセッシ、スタンリー・キューブリックも好きで、日本映画はあまり観ていなかったですね。黒澤明監督の作品は面白いと思っていたけど、小津安二郎作品は、子供の頃に観てもよく分からないじゃないですか。「眠い」とか思っていたけど(笑)。今観るとすごく面白いんですけどね。若い頃に憧れる作品って今とは全然違いますよね。
あと『ダイ・ハード』も大好きです。アクションでもリアル路線というか、人間くさい映画が好きで。ヒーローの価値観が変わったというか。これまでは、シュワルツネッガー、スタローン、ハリソン・フォードとかカッコいい俳優さんが活躍していたけれど、『ダイ・ハード』のジョン・マクレーンは口が悪かったりして。でも観ているうちにすごくカッコ良くて惹かれてしまう。映画にはそうやって、価値観を変える力を持っているんだなと感じます。
――監督はポン・ジュノ監督の助監督をされていましたが、ポン・ジュノ監督の現場から学んだことはどんなことですか?
「囚われすぎないこと」ですね。シーンごとにジャンルが変わるくらい自由に撮っているので、そういう所がすごく勉強になりました。ホラー映画だけど笑えるシーンが多いとか、今そういう映画は増えていると感じていますが、囚われずに自由に映画を撮るというこを、僕はポン・ジュノ監督から学びました。まだ『ガンニバル』は観られていないと思うので、ぜひ感想を聞いてみたいと思います。

「ガンニバル」はディズニープラス「スター」にて独占配信中。
インタビュー・テキスト:中村梢/撮影:SYN.PRODUCT/企画・編集:向井美帆(CREATIVE VILLAGE編集部)