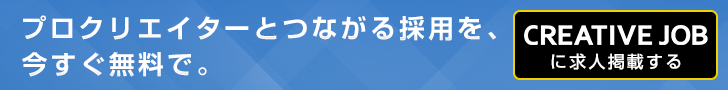――世界は多くの作品で満ちている。それを生み出すあまたのつくり手たち。そのなかで、独自のエネルギーを放つ人たちがいる。なぜつくることをあきらめなかったのか、現場に立ち続けるには何が必要なのか、どうすれば一歩でも次のステージに進むことができるのか。CREATIVE VILLAGEでは、最前線を走るトップクリエイターたちに作品、つくり手としての原点、そしてこれからを問う――
2021年実写映画興行収入No.1に輝いた映画「東京リベンジャーズ」。原作ファンからもっとも泣けると支持されるエピソード「血のハロウィン」を「運命」「決戦」の2部作で描く続編に、監督・英勉は相当の覚悟で挑んだ。「揺るぎない強い意志で、本当に高いところを目指して、役者さん、スタッフみんなでやってきました」。映画を完結させたいま、すべてを観客に託す。「僕たちの熱が必ず伝わるものになっていると思います」
1968年京都府生まれ。京都産業大学卒業後、92年東北新社に入社、CMディレクターとして活躍。2008年に映画「ハンサム★スーツ」で監督デビューを果たす。累積発行部数7000万部突破の人気マンガ『東京卍リベンジャーズ』を実写化した映画「東京リベンジャーズ」(21)は、最終興行収入45億円、動員数335万人の大ヒットを記録した。 主な作品に、映画「行け! 男子高校演劇部」(11)、「貞子 3D」(12)、「ヒロイン失格」(15)、「トリガール!」(17)、「あさひなぐ」(17)、「未成年だけどコドモじゃない」(17)、「3D 彼女、リアルガール」(18)、「映画 賭ケグルイ」(19)、「前田建設ファンタジー営業部」(20)、「ぐらんぶる」(20)、「映画 映像研には手を出すな!」(20)、「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」(21)、「おそ松さん」(22)、ドラマ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」(09)、ドラマW「稲垣家の喪主」(17)、配信ドラマ「No Activity/本日も異状なし」(21)ほか。
俳優陣には自由に思いっ切りやってほしかった
やり切った感はすごくあります。主人公のタケミチを演じる北村匠海くんはじめ俳優陣とスタッフ全員が、映画「東京リベンジャーズ2」をつくり上げよう、全うしようという強い意志と覚悟で臨んだ作品ですので、そのみんなの想いが実を結び、やっとみなさんに観ていただけるところまできた。本当に感慨深いです。第1作の映画「東京リベンジャーズ」(21)にお声がけいただいたのは、クランクイン(2020年3月)のちょうど1年前です。フジテレビの岡田翔太プロデューサーから原作マンガを渡され、読ませていただいたらめちゃくちゃ面白かった。ただ、ヤンキーなんて恐いし、そういう作品なら僕が監督というのは違うなと感じました。それで岡田さんに、「どういう映画をつくりたいんですか?」と尋ねたら「青春群像劇をやりたい」と。「だったらやれます」と応えました。それがスタートです。
そこから、脚本の高橋泉さん、KADOKAWAの稲葉尚人さん、岡田プロデューサーと僕の4人でひたすら話し合い映画の構成や脚本をつくり上げていきました。僕が一番描きたかったのは「仲間」です。原作を読んで感じたアツい友情やあふれ出る熱を生身の人間で表現したいと思いました。キャスティングは岡田プロデューサーです。考えを求められることもありますが、基本的に意見や要望は言いません。僕が考えるのは、決まった役者さんと原作のキャラクターとの相性、どうやってキャラクターを役者さん自身に引き込んでもらえるかということです。

第1作は撮影中から、「これはいける、面白い作品になる」という手応えはありました。俳優陣もスタッフも、とにかく熱のあるものをつくるんだと、僕の想像以上の熱量で最後までやり通してくれた。役者さんとスタッフみんなが同じ方向を向いているということがしっかり確認できてさえいれば、あとはみんなプロですから、こうしたほうがいいとか、こうやりたいというアイデアや意見が、役者さんからもスタッフからも出てくる。それを、特に俳優部に対しては、できる限り制限をかけず、やりたいように好きに動けますよという場をつくる。前作も本作でも、それが僕のやり方です。アクションや動きについては、撮影現場や事前の練習の際に、「僕はこう思うんだけど、どうやりたい?」と役者さんに聞いて、アクション部を含めてみんなで話し合いながら進めていきました。役者さんをあまり型に押し込めるとやりづらいだろうし、それではもったいない。せっかくこんなそうそうたるメンバーが集まっているわけだから、とにかく彼らに自由に思いっ切りやったと感じてほしいと思っていました。

匠海くんの覚悟に頭が下がりました
1作目が公開されてすぐのタイミングで、「2」をやりたいというお話をいただきました。「2」で描かれる「血のハロウィン」は原作的にはひとつの大きなピークを迎えるエピソードですので、実写化はとてつもなく大変だなと感じました。それで、「本当にやるんですか? ガチですか?」と(笑)。ただ、やるんだったら、僕らが原作を読んで体感したあの熱は絶対に損なわないようにしなければならないし、さらにプラスの何かを得られるような作品にしたいと思いました。それで僕も腹をくくりました。「2」は入り交じるさまざまなキャラクターのエピソードや感情をひとつに集約するというお話、つくりなのですが、それを匠海くん演じるタケミチという主人公に全部背負ってほしいと考えました。それで最初に匠海くんに、タケミチに何もかもを背負ってほしいし、そのタケミチを通してお客さんは映画を観る、そういう構造にしたいと話したら、「そのつもりです」と言ってくれた。その匠海くんの覚悟には頭が下がりました。「2」の撮影を通して一番強く印象に残っているのは、座長として、これほど複雑にいろいろな人間や感情がもつれ合った物語をひとりで背負い切ろうとしてくれた、それだけ覚悟を持って挑んでくれた匠海くんの姿です。

ほかのキャストの強い覚悟も現場で常に感じていました。前作よりもそれぞれのキャラクターの感情がより複雑に描かれているし、時代設定も4つぐらいに分かれていて、各時代に応じた演じ分けが必要とされるのですが、その細かいひとつひとつを役者さんたちは見事に演じてくれました。時代的に一番古い過去だと、東京卍會(とうきょうまんじかい)結成メンバーの6人しかいない、まだみんな若い頃の話なのですが、それをあれほどまでに鮮やかに見せてくれた。あれは僕が演出したというより、彼ら6人がその場でつくり出したもので、全員が同じ方向を向いて高い意識を持ってやってくれたからこそ実現したものだと思います。

「2」は、複雑なピースを重ねてつくり上げていったという意識を僕は強く持っています。それは、ひとつのピースが上手くいかなかったり違ったりすると壊れてしまいそうなほど繊細なバランス構造でした。ざっくり面白ければいいといった感じではなく、ワンシーン、ワンシーン、本当に小さなワンカット、ワンカットを丁寧に重ねていかなければならなかった。そこは大変でした。ただ、もともと脚本にあったことや頭の中で考えたものひとつひとつを、役者さんたちとスタッフみんながさらにパワーアップさせて、ワンカット、ワンカットつくり上げてくれていたので、大変ではありましたが、とても嬉しいというか、目の前にもっといいものが返ってくるというのは喜びでもありました。役者さん、そしてスタッフみんなのお陰でここまで来ることができました。いま一番思うことは、とにかく多くの方に観ていただきたいということです。原作ファンの人も、原作を知らない人にも、熱い想いを体感してもらえるという確信がありますし、それを早くみなさんに味わっていただきたいです。映画はお客さんに観てもらってこそですし、完成させたあとはもう映画はお客さんのものですから。

すべて一発勝負、本気です
僕が映画を観はじめたのは中学・高校時代からです。角川映画華やかなりし頃で、ハリウッド映画も観ていましたし、エンターテインメント作品が中心でした。仲間との遊びみたいなものでしたが、高校時代には友達が持っていた8ミリで自主映画も撮っていました。当時から映画業界への憧れのようなものはありました。というのも、薬師丸ひろ子さんの大ファンで、業界に入れば会えるんじゃないかという、よこしまな考えで。まだ薬師丸さんとは仕事したことがありません。お会いしたこともないんです。次こそは、なんて気持ちもありますが、会えたら、もうこの仕事辞めます。会えたときは引退のとき(笑)。そういうのって叶っちゃうとダメなんですよね、きっと。
大学時代は映画研究会に入って映画をつくり、映画館でバイトもしていましたし、映画漬けでした。でも映画を勉強しようとか、学ぼうといった感覚よりは、楽しいから、面白いから観るといった感じでした。映画監督になるんだという強い意志もなく、漠然と映画業界に入りたいとは思っていましたが、冷静に考えたら、どうやって映画監督になるのか、どうすれば映画で食べていけるのか、検討もつきませんでした。それで大学卒業後は、最先端の映像を撮っていると当時感じていたCM業界を志望し東北新社に入社しました。ディレクター志望でしたが、演出部の採用はないと言われ、最初は制作部で4年ほどプロダクションマネージャーをやっていました。そこで僕の師匠であるCMディレクターの中島信也さんの現場を担当していたご縁で企画演出部への異動が叶い、CMディレクターとして長く活動してきました。僕は完全に受注型です。プロデューサーがどういうものをつくりたいのかという大前提に対して、どんなことができるか、どうすればそれを実現させることができるのかということを考えています。自分から仕掛けるようなことはあまりしません。

これまでに転機となった作品や出会いは、言ってしまえばすべて。全部一発勝負、本気です。ひとつひとつベストを尽くしたい。でも条件的には叶わないこともあって、ベストが無理なら次はベターを考えないとダメだとなり、そうやっていくうちに、最初の大目標からずれてしまっているということもある。そのうちに、「面倒だな、流すか」となり、まあまあなとこで落ち着かせようとしてしまう。でもやっぱりそれって作品に響く。1点ずつ作品の点数が減っていってしまうんです。だから流さない。ヘトヘトにはなりますが。流すと大変な目に遭いますし、ろくなことがないんです。
見上げるような想いで付き合ってきました
映画監督としてお声がけいただけることをとてもありがたいと思っています。どうすれば映画監督になれるのか、続けていけるのか、方法や秘訣はないと思います。なり方なんて千差万別だし、それは演出方法も同じです。師匠のような人がいて習うことはできても、結局はその人間の中から出てくるものなので、やっぱり人それぞれなんです。学んだ手法をひとつひとつ試してやってみて、状況に合わせて柔軟に自分をいろいろに変えていくというやり方がひとつにはあると思います。それとは別に、確固たる揺るがない自分というものを持って、完全に自分の力で引っ張っていくという手もある。僕はそのふたつのブレンドです。現場での絶対的なポリシーなんてないし、役者さんたちやスタッフから意見が出やすい環境をつくりたいとは思っていますが、でもそれにはスケジュール的に許されるという絶対条件があって、1日に脚本何十ページも撮らないといけない現場で、みんなの意見をその場その場で聞いていては撮り切れない。こうやりますって言ってバッと撮らなきゃ終わらないわけです。だから、揺るがないものと柔軟性を条件によって組み合わせる、それが僕のやり方です。ひょっとしたら僕は、クリエイターというより、いろんなバランスを取って方向性を出しているだけなのかもしれません。

役者さんみんなが口々に、映画「東京リベンジャーズ」をつくり上げた誇りや、参加できたことへの感謝を語ってくれます。本当にありがたいことです。みんな僕なんかより考えていることは深いし、アイデア豊かですし、横に並ぶなんて恐れ多いと一歩後ろに下がって見上げるような想いで彼らと付き合ってきました。僕にとって映画「東京リベンジャーズ2」とは……大きな山でした。そのはるか彼方のてっぺんを目指し、みんなで一歩一歩登ろうとした、そして登ってきた大きな山です。最後のほうは後ろからみんなに押してもらって、「ありがとうございます、すみません」なんて言いながら(笑)。みんなで挑んだ、本当に、とてつもなく大きな大きな山でした。
東卍崩壊の危機をもたらす、かつての親友同士の壮絶な戦いがついに始まった。マイキーは敵の芭流覇羅(ばるはら)に寝返った場地を連れ戻すために。芭流覇羅にいる一虎は東卍をぶっ潰し、マイキーを殺すために。マイキーの兄・真一郎の死により壊れてしまった東卍結成メンバーたちの絆。「もう、誰も死なせたくない!」それぞれの想いを受け止め、タケミチは、明るい未来のため、最悪の結末を止められるのか! そして、もう一度ヒナタを、仲間の未来を救えるのか———。




原作:和久井健『東京卍リベンジャーズ』(講談社 「週刊少年マガジン」KC)
出演:北村匠海、山田裕貴、杉野遥亮、今田美桜、眞栄田郷敦、清水尋也、磯村勇斗、永山絢斗、村上虹郎、高杉真宙、間宮祥太朗、吉沢亮
脚本:髙橋泉、音楽:やまだ豊
プロデューサー:岡田翔太、稲葉尚人、撮影:江崎朋生、照明:三善章誉、録音:加来昭彦、美術:佐久嶋依里、加藤たく郎、衣装:宮本まさ江、ヘアメイクディレクション:須田理恵、編集:相良直一郎、アクションコーディネーター:諸鍛治裕太
Ⓒ和久井健/講談社 Ⓒ2023 フジテレビジョン ワーナー・ブラザース映画 講談社
PG12
全国公開中
インタビュー・テキスト:永瀬由佳