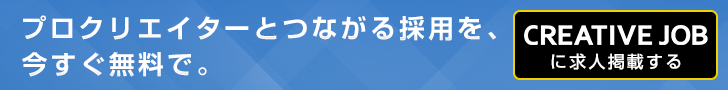――世界は多くの作品で満ちている。それを生み出すあまたのつくり手たち。そのなかで、独自のエネルギーを放つ人たちがいる。なぜつくることをあきらめなかったのか、現場に立ち続けるには何が必要なのか、どうすれば一歩でも次のステージに進むことができるのか。CREATIVE VILLAGEでは、最前線を走るトップクリエイターたちに作品、つくり手としての原点、そしてこれからを問う。――
2014年に公開され大ヒットを記録した韓国映画「最後まで行く」。リメイクに挑んだ監督・藤井道人は、人間の愚かさまでも見事に笑いへと昇華させた。可能にしたのは、素晴らしい役者たちと理解あるプロデューサー陣、そして長年現場を共にする盟友たちの存在だった。どんな仕事にも通ずる大切なことは「謙虚さ」だと藤井は語る。謙虚に粛々と努力すること。その姿が出会いと運を運ぶ。それが生半可なものでなければ、見てくれている人は必ずいる。
好き勝手に、思い通りやらせていただきました
お話をいただいたのは、映画「新聞記者」(19)の公開直後でした。映画「余命10年」(22)の撮影がすでに決まっていたこともあって、正反対の突き抜けたような映画を撮りたいという思いが強くありました。僕自体ノンストップエンターテイメントが好きで、韓国映画も大好きなんです。まさに本作はそんな大ヒット韓国映画のリメイクなのですが、監督人生でリメイク作品をやれる機会なんてそうはないと思いますし、本作が面白ければ、オリジナルの韓国映画にも興味を持ってくれる人も出てくるでしょうし、そういう相乗効果も期待できる。そのためにも自分たちなりのものをしっかり届けることが大切だから、オリジナルを手がけた韓国のスタッフのみなさんに最大限のリスペクトを払いながら、好き勝手に思い通りやらせていただきました。

撮影は全カット大変でした。まず冒頭、師走の大雨の夜、岡田准一さん演じる刑事の工藤が事故を起こすシーン。岡田さんの運転する車、それを牽引する車、横には散水車、それらをクレーンに乗った撮影チームが後ろから追いかけ回り込みと、疾走する車だらけのシーンをワンカットで撮りました。クランクインして初めての撮影がそのシーンです。冒頭の5分で引き込まれるかどうか、僕はそれをけっこう判断基準にしているんです。だからとにかく今回は「最初から行くぞ!」という感じで、最初の5分で、「どうする岡田准一!」ってものを絶対にセットアップしたいと思いました。入りはとても静かに、でも何か怪しい、何か起きそう、いや起きないのか、やっぱ起きた!みたいな駆け引きをここまで揺さぶった演出は初めてでした。冒頭が土砂降りなだけに、次の検問のシーンでも大雨を降らせなきゃいけない。クランクインが昨年1月でしたので、夜の気温はマイナスまで下がり路面は凍結するし、そのようななか、国民的スターの岡田さんをずぶ濡れにして延々撮るという、ラストまでそんな過酷なアクションシーンの連続です。そのすべてにこだわり抜いてやらせていただきました。本当に楽しかったですが、本当に大変でした。
全身全霊をかけてくれる岡田さんと綾野さんだからこそできた
空撮は僕たちのチームの特色のひとつかもしれません。撮影にはドローンを多用しています。こんなに世界は広く、俯瞰して見たらとてもちっぽけな存在かもしれないけれど、それでも地面をはいつくばって生きている人たちをちゃんと表現したい、そういった情感を映し出したいと思っています。4月に公開された映画「ヴィレッジ」もそうです。撮影は「最後まで行く」が先で、すぐあとに「ヴィレッジ」だったのですが、僕自身この2作をよく比較して考えています。日本人には、慣習やルール、歴史を崇拝する文化があって、そこには功罪もある。そういうことを「ヴィレッジ」ではプロデューサーの河村光庸さんとかなり話し合いました。
「最後まで行く」は、「これやったら面白いですよね」ってことを、みんなで議論しながら、『面白い』を追求しました。狭いコミュニティーを出られない人たちを描いたという点では同じなのですが、「ヴィレッジ」は内に内に向かう話で寓話的な側面もあって、河村さんの強い思いで成立した作品です。河村さんの思い「映画を言語として人に問いかけたい」「時代というものに対して問題提起したい」―― 僕はそう理解して挑戦したつもりです。対して「最後まで行く」は、岡田さんと綾野剛さんの新境地、困った四十路はこんなに面白いという詰んでるふたりをただただ楽しんでほしい、難しいことは何も考えないで観てくださいという映画です。「藤井作品だから考えさせる系でしょう?」と思っている人もいるかもしれませんが、何も考えさせません(笑)。そこは期待して観てほしいです。

岡田さんは本当に素晴らしかったです。初めてお会いしたときの岡田さんはやっぱりカッコいいんです。でも今回は、「木更津キャッツアイ」のような、一生懸命だけどうまくいかない、キュートでダメな岡田さんを撮りたいと言ったら、「わかりました」と。髭も生やすし、髪型も変え、ご自身から進んでダメ人間に。僕のどんな要求にも「できない」なんて絶対に言わないし、弱音も決して吐かない。それは綾野さんも同じです。闘いのシーンについても、岡田さんには本当に教えられました。岡田さんは、この役、こういう人間だったらどう動く、どう闘うかということを考えている。本作では「トカゲ」がある種のモチーフになっているのですが、岡田さんの提案ではいつくばって動く岡田さん演じる工藤のシーンが追加されましたし、身体を駆使したアクションの演出が岡田さんはとにかくすごい。「藤井くん、どっちにしたい?カッコよくもできるし、泥試合もできるよ」「泥でお願いします」「了解」みたいな感じで、最後の墓地での岡田さんと綾野さんのドロドロの闘いも実現しました。
僕は毎回作品のテーマを考えるのですが、本作は「埃」。最後、闘う埃まみれのふたりに降る雪。埃が白い雪に変わるというか、人間は誇りだったり地位だったりに固執して生きているけれど、そんなものは墓の下に入ってしまえばみんな同じ、平等なのだと、僕自身はそんなことを考えていたのですが、ふたりの壮絶な対決を見ていると、そんなことどうでもよくなって、大晦日に何やってんのコイツら!ってもう笑うしかない。必死のふたりが滑稽に思えるのは、ふたりが本気で生きようとしているからで、目的やなぜ自分たちは闘っているかを、岡田さんと綾野さんが本当に忘れて闘ってくれたからだと思うんです。1本の映画にここまで全身全霊をかけてくださるふたりだからこそできた作品です。

敬意を持って人に接する
僕の映画の原体験はTSUTAYAです。自宅から徒歩1分のところにTSUTAYAができて借りて観るようになり、友だちとも映画の話で盛り上がったり、そこから映画が好きになりました。高校生の頃には毎日1本は観ていました。ベン・スティラーやアダム・サンドラー、ジム・キャリーが出ているちょっとおバカなアメリカンコメディが大好きで、友だちと大笑いしながら観ると楽しいんです。それから映画自体に興味を持つようになり、当時はミニシアターブームでしたので、アート系の作品も観るようになりました。高校卒業後は日本大学芸術学部映画学科の脚本コースに進みました。国語が好きで、文章を書くことも得意でしたので、宮藤官九郎さんのような脚本家になりたいと思っていました。それが、大学で自主映画サークルに入って映画を撮るようになってから、監督に魅力を感じるようになりました。僕はずっと剣道をやっていたのですが、剣道って自分が勝つか負けるか、個人戦だし勝敗もはっきりしている。でも映画というのはも正解のない生き物のようで、それにみんなで対峙し協力してつくりあげていくことに大きな喜びを感じました。いまもその大学の仲間たちと一緒に映画をつくっています。

「最後まで行く」の撮影を手がけた今村圭佑も、いまや日本を代表する若手カメラマンぶってますけど、ただの大学のサークルの後輩です(笑)。文化祭のような楽しさが僕の映画づくりの原点にあって、いまもそれが続いているような感じです。僕らは大学ではみ出し者でした。授業にもろくに出ないで遊んだり、自主映画ばかり撮っていました。サークル仲間と立ち上げた「BABEL LABEL」の代表・山田久人とは、大学の入学式のバス移動のときから一緒です。当時僕は派手な金髪で、そのとき脚本コースは女性が多くてみんな知的な感じで、その中にヒップホップのダボッとした服にB-BOYキャップのそぐわないヤツがいて。向こうも思ったはずです、「そぐわないヤツがいる」と(笑)。それで「よろしくお願いしまーす」って隣りに座って、それからずっと仲良くやっています。そんな仲間に大学で出会えたこと、それは僕の運です。
運をよくするためには、人に敬意を持って接することだと思います。それは父親の教えです。やさしくも厳しく、義にあふれた人で、「嘘をつくな」「金は借りるな」「女性に暴力を振るうな」、この3つだけちゃんと守ればあとは何をしてもいいと言われて育ちました。その3つを守っていると、自然と人が周りに集まってきましたし、みんな他人にやさしいいいヤツらです。映画業界はかつて「夢の工場」と言われていた。僕らはそれを復活させたいと思っています。精神的にも経済的にも保障され、安心して存分に才能を発揮し映画づくりに向かえる環境を整えたい。ビジョンを掲げてやる以上は、正解か不正解かを仲間たちと確認しながら徹底的にそこに向かう。ひとりだとできないことってたくさんあるのですが、ちょっと青臭いですけど、仲間に支えられていますし、いてくれて本当によかったと思っています。
まず、自分を特別だと思わないこと
劇場監督デビュー作品「オー! ファーザー」(14)に僕を引っ張っていただいたプロデューサーの奥山和由さんには感謝しかありません。大学の文化祭のトークショーに奥山さんがゲストで来られていたときに、脚本を書ける若者を集めたいといった話をされていて、「興味ある?」とどなたかに声をかけていただいて、それでしばらく奥山さんのところでプロットライターをやっていました。そのときに書いた1本が伊坂幸太郎先生の「オー! ファーザー」でした。伊坂先生が脚本は彼にお願いしたいと言ってくださって脚本家デビューが決まりました。それが東日本大震災で撮影が延期になってしまったことで監督もやらせてもらえることになった。奥山さん、伊坂先生への感謝とともに、そこで結果が出せなかった悔しさみたいなものもいまでも残っています。
もうひとり、最初にもお話しした「ヴィレッジ」のプロデューサーの河村光庸さんとの出会いは衝撃的でした。河村さんとは映画「新聞記者」(19)で初めてご一緒させていただいたのですが、河村さんの言葉で大事にしているのは「監督がカッコ悪いのはダメだ」ということです。監督が貧乏だとみんな貧乏になると。「新聞記者」のギャラはそんなによくなかったような気がしますが(笑)、監督を食わせるということに必死に頑張ってくれた人でした。山師みたいなところもあって怪しいなって思うことも多々ありましたけど、河村さんの映画にかける思いや僕に対する愛情の強さと深さ。映画人としての師匠でもあり、それ以上に親のように大好きな人でした。

いまつくり手として思い悩んでいる人がいるとしたら、まず一番に、自分を特別だと思わないことだと思います。何かできるはずだとか自分に期待すると、それに応えられない自分に嫌悪感が生まれてしまう。自分はみんなのおかげでいまここにいるんだという気持ちを常に持つことが、実は一番いい仕事をする近道なのだと、それは本当にこの仕事をやってきて気づいたことです。「藤井はなぜあんなに撮ってるんだ?」って思われることもあるかもしれませんが、20代仕事がなくて食えなくて恥ずかしい思いもたくさんしました。だから、求められるうちが花だと思っていますし、ただ明確な線引きとして、同じような作品はやらないと決めています。逆にこれまで見たこともないようなオファーしてくださる方の期待にはなるべく応えたい。僕と一緒にギャンブルしたいと思ってくれているんだな、頭の中大丈夫かな、この人って思いながら(笑)。
映画もドラマも配信もどれも好きだしやりたいのですが、僕が生まれる前から映画もテレビドラマもあって、そこには長い歴史がある。つまり僕が生まれてから登場したのは配信だけなんです。だから配信の開拓者にはなれる自信がある。そこに対してのアプローチは絶対にやめたくないし、海外でもデヴィッド・フィンチャーといった名だたる監督たちが、配信ドラマにハリウッドの手法を持ち込んで面白い作品をどんどん手がけていて素晴らしいなと。僕もいいものは貪欲に取り入れながら、日本人として果敢に攻めていきたいと思っています。
「遊びに来ている感覚」が現場には大事
いま仲間たちとよく話していることは、撮影時間とギャラの問題を見て見ぬふりしないことです。自分が呼んだスタッフが実はとても安くオファーされていたことを僕は知らずにお願いしてしまっていたことが多々あったんです。日本人ってギャラについて隠すところがありますが、それは間違っていると思います。もっと公にすべき問題だし、ハラスメントなんてないのが当たり前、もうそのレベルの議論なんてしたくないんですよね。時間についても、撮影は「おはようございます」と現場に入ってから最後のカットまで12時間。それと食事は4種類。台湾のロケでは食事は温かいが大前提で、朝昼晩すべて8種類もあるんです。監督も現場に入ったばかりの人も関係なく並んだ順に美味しい食事にありつけるから、みんなウキウキしながら行列をつくる。その感じがすごくよくて。8種類あると大体失敗して僕は痛い目に遭っていたから、まず4種類を目指そうかと(笑)。
本作の日活のプロデューサーの西村信次郎さんも、変えられない壁を変えようとしてくれる人です。そういう方たちの力を借りながら、このひと手間が相手への配慮につながるなら、できることはやる、気づいたことは変える。その努力を惜しみなく続けていきたい。僕たちの現場は楽しいですよ。仲間たちとゲームセンターで遊んでいるとまではいかないですが、その「遊びにきている感覚」ってものすごく大事で、遊びだとみんな寝坊しないし、ワクワクしながら来ますよね。でも、やらされているとか緊張感で張り詰めた現場だとそうはならない。藤井の現場はご飯も美味しいし楽しい。その楽しさのなかにも厳しさがあって、しっかりいいものをつくっている。まずはそういう現場づくりを実現させるところからだと思っています。

映画づくりを僕は船の旅だと思っているんです。無事にひとつの航海を終えたら、また次の目的地に向かって船を出す。いろんな旅があればあるほど楽しいし、そんな旅に信頼する仲間とキャストと一緒に出られているなんて本当に恵まれていると思っています。僕らは問題児ばかりのチームだと自負しているのですが、映画「最後まで行く」は、そんな僕たちが最高に暴れてつくった作品です。みなさんがこれまで見たことのない、愚かでキュートな岡田准一と綾野剛をとにかく笑ってください。辛い思いや抱えているいろんな嫌なことも、このふたりを見たら笑っちゃってちょっと忘れられると思います。コイツらよりはマシだって。
1986年東京都生まれ。日本大学芸術学部映画学科脚本コース卒業。大学卒業後、2010年に映像集団「BABEL LABEL」を設立。脚本も手がけた映画「オー!ファーザー」(14)で劇場長編監督デビュー。映画「新聞記者」(監督・脚本/19)で日本アカデミー賞最優秀賞3部門を含む6部門、毎日映画コンクール日本映画優秀賞等多数の映画賞を受賞。主な作品に、映画「青の帰り道」 (監督・脚本/18)、「デイアンドナイト」(監督・脚本/18)、「宇宙でいちばんあかるい屋根」(監督・脚本/20)、「ヤクザと家族」(監督・脚本/21)、「余命10年」(監督/22)、「ヴィレッジ」(監督・脚本/23) 、アニメーション映画「攻殻機動隊 SAC_2045 持続可能戦争」(監督/21)、ドラマ「アバランチ」(21)、「封刃師」(22)、「新聞記者」(Netflix/22)、「インフォーマ」(TV・Netflix/23)ほか。
年の瀬迫る12月29日の大雨の夜。刑事の工藤(岡田准一)は危篤の母のもとに向かうため車を飛ばしていた。そんなときに署長から電話が入り署のウラ金問題への関与を疑われ焦りでいっぱいになる。さらに別居中の妻・美沙子(広末涼子)から母が亡くなったとの連絡が。突然車の前に現れる男。避けきれずはね飛ばしてしまった工藤は遺体を車のトランクに入れ立ち去る。一方、県警本部の監察官・矢崎(綾野剛)は行方不明となったある男を追って工藤に迫っていた。


プロデューサー:西村信次郎 加茂義隆 小出真佐樹、ラインプロデューサー:和氣俊之、撮影:今村圭佑、照明:平山達弥、録音:根本飛鳥、美術:宮守由衣、装飾:石上淳一、衣裳:宮本まさ江、ヘアメイク:橋本申二、編集:古川達馬、VFXスーパーバイザー:大澤宏二郎、スーパーヴァイジングサウンドエディター:勝俣まさとし、リレコーディングミキサー:浜田洋輔、助監督:逢坂元、制作担当:阿部史嗣 宮森隆介、キャスティング:杉野剛
©2023映画「最後まで行く」製作委員会
2023年5月19日より全国ロードショー
インタビュー・テキスト:永瀬由佳