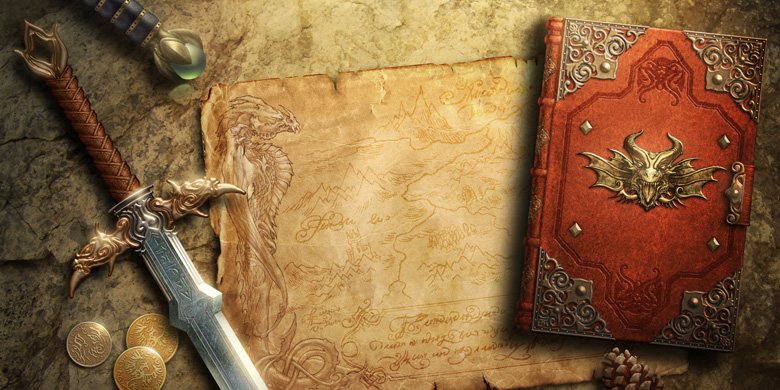――ユーザーの操作に直接的にかかわる分野を担当する存在として、ゲーム制作においてますます重要性が認知されているUIデザイナー。株式会社カプコンでは2006年に専門の部署を立ち上げて以降、UIデザインの定義や人材育成などを進め、現在では70名を超えるUIデザイナーが専門職として活躍している。今回は、『デビルメイクライ4』や『ゴースト トリック』といった人気作品にUIデザイナーとしてかかわり、現在はカプコンのUIデザイン室で室長を務める植田雅生さんにその魅力や必要な技能を聞いた。――
1994年株式会社カプコン入社。2Dキャラクター、アニメーション、3Dモデルなどの経験の後、UIデザイナーに転向。デビルメイクライ4、ゴーストトリック、エクストルーパーズのUIを制作、以降ストリートファイター5など複数のタイトルにてUIディレクションやデザイナーの進行管理を行う。並行してUIデザイン部門、アート、グラフィックデザイン部門の組織構築や採用育成などのマネジメント業務に従事。
難しいからこそ100点に近いものを目指す
――植田さんが担当されている”UIデザイナー”という職種について、改めて教えていただけますか。
言葉の通り、ユーザーが直接触れることになるUI=ユーザーインターフェイスのデザイン全般を担当しています。また、世界中の人に楽しんでいただけるよう、言語が変わっても遊びやすいようにすることも大きな仕事です。ゲームをより面白く遊んでもらうために、料理で例えるなら、箸を使うのがいいのかそれとも別のもので食べるのがいいのかなども含めて、ゲーム内のプレイ体験をコーディネートする役割と言えるのかもしれません。
――94年にカプコンに入社された際は、UIデザインとは違うお仕事をされていたそうですね。どのようにして、現在のお仕事にかかわるようになったのでしょう?
カプコンでUIデザインが専門職になったのは2006年頃で、それまで自分は2Dのキャラクターデザイナーとしてドットを打つ仕事をしたり、時代が進んで3Dに移り変わっていくなかで3Dキャラクターのモデラ―(『ジャスティス学園』や『バイオハザードアウトブレイク』など)を担当したりしていました。ですが、どんどんモデル制作面が進化して、スペックが上がっていく中で、「この先ついていけるだろうか」という不安も感じていました。そんなとき、UIデザイン専門の部署が立ち上がる話を聞いて、ジョブチェンジしてみようと思ったのがきっかけです。自分自身、イラストを描くことはもちろん好きでしたが、学生時代はグラフィックデザインを学んでいたり、独学でウェブデザインを学んでいたりしていたので、むしろレイアウトを組んだりすることの方が好きなタイプだったんです。

――当時は、まだまだUIデザインの重要性が認知されていなかった時代だったと思います。その中で、UIデザインにどんな魅力を感じたのでしょう?
確かに、当時はまだiPhoneのような製品が世間に出回る前で、UIやUXという言葉を聞く機会もあまりなかった時代でした。ですが、自分の場合は、画面の構成や配置を考えることに興味があったので、そういう意味でも楽しいと思える仕事だったのかもしれません。UIというのは、なかなか万人にとっての100点を取ることが難しい分野で、100点だと(ユーザー視点では自然に感じられるため)褒められることはなく、一方で99点だと文句を言われてしまう仕事でもあります(笑)。ですが、多くの人にとって100点に近いものを目指すのは、一見地味なようでいて、とても大切でおもしろい仕事だと思っています。
――植田さんが最初にUIを担当された『デビルメイクライ4』を含めて、UIデザインを行なっていくなかで試行錯誤したことや工夫したことを教えてください。
『デビルメイクライ4』(2008年)は初めてUIデザインを担当したこともあり、まだ使い勝手よりも見た目のデザインを意識していた部分が大きかったと思います。とはいえ、今でいうところのUXが向上したと思えるような工夫もありました。あの作品はPlayStation 3とXboxでの発売でしたが、当時ちょうどプレステ3のコントローラー(のL2&R2ボタン)がトリガー式になって、『デビル4』でも新たに登場した主人公ネロの武器がバイクのアクセルをふかすような動作を持った近接武器だったので、UIデザインとしてもアクセルをふかすようなデザインをゲージに盛り込んでみました。この部分は、遊びとコントローラーの仕組みとが連動したものになっていたと思います。
――ユーザーの操作と連動している、とてもUIデザイナーらしい発想ですね。
とはいえ、当時はそこまでロジックをもってUIをデザインしていたわけではなく、見た目としていいものを追求した結果、遊びの向上にも繋がったという感覚でした。メニュー画面にシルバーアクセサリー的なモチーフを入れているのも、ゲームの世界観やキャラクターたちの服装に合うように、あえてゴテゴテなデザインにしていった結果でした。一方で、『ゴースト トリック』(2010年)はハードがニンテンドーDSに変わって「タッチができる」ようになったので、UIとしても「触れて楽しめる」ことを考える必要が出てきました。デザインとしては『デビルメイクライ4』とは真逆の、ポップなグラフィックを使ったシンプルなものですが、当時はまだゲームで表現できる解像度があまり高くなかった中で細かいアニメーションをつくりこんだり、より良く見えるようにドット修正したりしてたので、なかなか大変な作業でもありました。この辺りは、昔から2Dをやってきた経験が生きたかもしれないですね。

UIデザインをロジックで考える、カプコンのUIデザイン室の役割
――印象的だったタイトルなどがあれば教えてください。
やはり、最初に自分が最初から最後までUIを担当した『デビルメイクライ4』は一番思い出に残っていますし、外部に制作いただいて初めて監修として入った『ストリートファイターV』(2016年)は、自分は直接手を動かしてはいないですが、ディレクターや外部の方と連携しながらつくっていくという意味で初めての経験になりました。あとは、『Dragon’s Dogma』(2012年)についても、自分が直接何かをしたわけではないですが、周りをサポートする形でUI周りを調整したり、UIチームが「これがいい」と言っているものに対して、プロデューサーやディレクターが難色を示した際、その間に入って調整したりするような第三者的な役割を担当していました。
――お話を聞くと、UIデザイナーとして働くには様々な分野の知識が要りそうですね。
私たちはビジュアルを作りこむ事と並行して、「どうすれば遊びとして心地よくプレイできるか」という部分を大切にしていて、様々な役割の人々が自分なりの「いいもの」を持ち寄ってゲームをつくっている中で、UIに関しては最終的に「こうしましょう」と決断する必要が出てきます。また描画やフォントの取り扱いなどUI固有の知識も必要になってきます。そのため、一通りの事をやれと言われてもなかなかすぐにできない仕事ではあるのかもしれません。最近はUIデザイナーとして入ってくる新人もたくさんいるのですが、苦労することもたくさんあるんだろうな、とは思いますね。
――カプコンさんは、2010年頃からUIデザイナーの育成に力を入れていらっしゃいますね。
弊社では中途採用が少なく、外部の方にお任せすることもあまり多くないので、新卒の段階から自社で採用して育成することを大切にしています。最初はUIの表層部分にかかわることしかしていませんでしたが、よりUIの根幹部分にあたる「どういう設計にすれば心地よいユーザー体験になるか」に焦点を当てはじめたのが、今に繋がる変化になりました。また、徐々にUIという言葉が浸透して、「UIデザイナーを目指したい」という学生が出てきてくれるようになったことで、人材育成もよりしやすくなった感覚はあります。とはいえ、サービスデザインとしてのUIとゲームのUIは似ているようで重視するところがまったく違ってくるので、「入社してからがスタート」が基本だと思います。

――一般的なサービスデザインとゲームのUIデザインはどう違うのでしょう?
サービスのUIデザインはゴールが明確で、たとえば料理のアプリなら、「どういう食材を買って、どういう手順で料理をつくればいいか伝える」という目的がはっきりしています。ユーザーは最終的に料理がつくりたいわけですから、そこに行きつくための情報を的確に与えることが仕事になるわけです。ですが、ゲームの場合は、ユーザーの行動に関して便利な要素だけを追求することが本当に楽しいゲーム体験になるのかというと、必ずしもそうではないと思うんです。というのも、ときにはあえてストレスを感じてもらうことも、ゲーム体験を面白くする要素のひとつになる場合がありますから。
――「簡単にクリアできるゲームは面白いのか」ということにも通じるお話ですね。
そうですね。ユーザーに対して便利な情報を与えることだけが、ゲームのUIデザインとしては最適解ではありません。また時にはユーザーが今まで経験したことの無い体験を与える事もありますし、ゲームはプロダクトでありながらディレクターの作品という側面もあるので独自の個性を出す事もあったりします。そういう意味で情報設計の考え方やアプローチ方法が全然違いますが、それが難しくもあり面白いところでもあると思います。
――また、技術の進歩にあわせて仕事内容をアップデートする必要もありそうです。
技術が進化すると当然やるべきことも増えますし、UIデザインに関しても難易度が劇的に上がってきています。実際のところ、UIデザインの分野でもすべての人が全ての領域を担当できるかというと、これはもう難しくなっているのが現状で、「若いからついていける/歳を取っているからついていけない」という話ではなく、必要となる技能が多岐に亘るため、そもそも現実的に難しい状態になってきています。そこで、弊社のUIデザイン室ではUIデザイナーとしての領域を定義づけしつつ、その中でさらに「職能」という形でそれぞれに役割を分解して、メンバー全員に理解してもらうことにしました。UIデザイナーの中でさらにそれぞれの能力を定義付けして、自分の強みを生かしてもらうということを、組織的に行なえるような仕組みにしているんです。

――具体的にはどんな役割があるのでしょうか?
たとえば、最近ではUIを実装するときに、よりプログラムに触れなければいけない場面が増えるようになり、プログラマーに実現したいUIを的確に伝える必要が出てきました。そこで、デザイナー側からもそういった領域をカバーするために、TA(テクニカルアーティスト)的な人材を置いたり、実装に強い人間を置いたりする必要が出てきています。このような技術面が得意な人材が必要である一方で、もちろん、よりビジュアル制作面が得意な人材も必要となるので、それぞれの強みを生かして仕事ができるような環境を整えることが大切です。そこで職能を5つに分けて、UIデザイナーの中でもどういう仕事にはまるかということを、入社後に調整できるような仕組みにしています。
――自分が得意な分野に関わることができる環境になっているのですね。
そうです。とはいえ、「UIとは何か?」という根本にあたる部分については、それぞれがしっかりと持っていてほしいとも思っています。野球で言えば、ピッチャーやキャッチャー、内野、外野などポジションごとに専門性は違っても、おおもとの野球のルールについては共通して深く知っているようなイメージです。また、答えはひとつではないので、「こういう場合はこれがいいんじゃないか」「こんな方法もあるんじゃないか」と、色々な発想を持ってほしいとも思っています。ゲームのUIはエンターテインメント性も重要なので、「利便性ではこの方がいい」と分かっていても、実はそこから大回りしたところに、ユーザー体験としては意味のあるものが出てきたりしますから。「まともに考えればこうでしょう」というものとは大きく違うところに、「こんな方法があったのか」という可能性が眠っていたりもするんですよ。

ゲーム制作が多様化する時代に。植田さんが感じるUIデザインのこれから
――植田さんご自身は、UIデザイナーとしての能力を鍛えるために日頃から意識されてきたことはありますか?
ゲームに限らずですが、世の中にある様々なものについて「なぜこうなっているんだろう?」と考えたり分析したりしていると、「この製品はこういう意図で設計されたのか」とか、たとえ結果的には上手くいっていないものであっても「本来はこういう意図で設計したものの、不完全燃焼でこうなってしまったのかな」とか、色々なことを推察できる瞬間があります。そんなふうに、たとえ結果として使いにくいUIになっていたとしても、いわゆるクソUIという言葉で片づけてしまうのではなく、その製品が設計されたプロセスにまで目を向けると、自分の中にもストックが増えていくように感じます。誰も最初から使いにくいUIをつくろうと思ってはいないですから、その誰かの経験は、自分が何かをつくる際にも糧になると思うんです。「これがいいのはなぜか/悪いのはなぜか」という、アウトプットまでのプロセスを考えるようにしている部分はあるかもしれません。
――様々なものを見て、その仕組みをロジカルに考えることがお仕事にも繋がるのですね。最後に、UIデザイナーの今後について感じていることがあれば教えてください。
最近はゲームの開発の規模がどんどん大きくなっていて、AAAタイトルだと開発規模はさらに膨大になりますし、今後ハードが変化すれば求められるスペックや作業量はさらに増えることが予想されます。多言語展開をする際の言語対応やカルチャライズについても、UIデザインの面からも考えていく必要がありますし、ユニバーサルデザインについても追及していかなければならないと考えています。マルチプラットフォームの場合も、様々なハードやプレイ環境を想定したUIデザインでなければいけません。そうなってくると、今までと同じつくりかたで、工程が増えるたびに人を増やしてマンパワーで何とかするという方法は、現実的ではありません。そこで、どうやって効率化して、コストを下げながらつくっていくかという部分をより考えていく必要が出てきます。そのためUIデザイン室で職能として定義しているIA(インフォメーションアーキテクツ)や、実装をしっかりつくっていくデータデザイナーといった職能に関しては、人材育成により力をいれていこうと思っています。これはなぜかというと、プランナーがそれぞれにいいと思って考えてきたシステムに関して、その整合性をしっかり取りながら、UIとしてどんなふうに整理して体験向上に繋げるかという部分を仕様書に落とし込めれば、制作面のコストを下げることに繋がると思うからです。同時に、プログラマーの気持ちを理解できる人材も育成して、UIをゲームに実装していく。この入り口と出口の部分をしっかりと支えることで、同じコストをかけた場合でも、手戻りが減ってしっかりといいものがつくれるんじゃないか、という仮定を持っています。そうやって少ない労力でいいものをつくることができれば、より細部に目を向けて作りこんでいく事も考えられますし、最終的にはユーザーのみなさんのゲーム体験向上に繋げられるのではと思っています。

3/27(木)に植田氏登壇「これからのデザインと組織論」セミナー開催

3/27(木)に開催する植田氏登壇のウェビナーでは、UIデザインの進化や、組織デザインのあり方 について、C&R社の事例も交えながらディスカッションを開催!また、C&R社 PlaNetStudio の 小林圭介氏、立澤英樹氏 にもご登壇いただき、技術的な観点・組織運営の視点から、より実践的なトークセッションを展開します。
インタビュー・テキスト:杉山仁