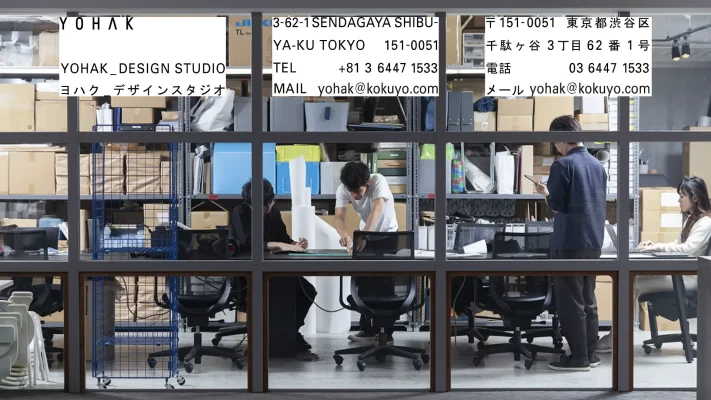人気ロックバンド「THE ALFEE」のリーダーであり、小説家としても活躍する高見沢俊彦さんが、2025年3月29日、東京都中央区・銀座 蔦屋書店で開催された「海ノ民話アニメーション2024完成披露イベント」の特別トークショーに登壇した。
このイベントは、日本財団と一般社団法人日本昔ばなし協会が進める「海ノ民話のまちプロジェクト」の一環で、海と人との関わりを描いた日本各地の民話をアニメーション化し、次世代へと語り継ぐ取り組みである。
当日は高見沢さんのほか、民謡研究家の佐藤千春さん、日本財団常務理事の海野光行氏が登壇。それぞれの視点から民話の魅力や価値、さらには現代における民話の創作について語り合った。
アニメが伝える「海ノ民話」の力
イベントはプロジェクトの紹介映像と2024年度制作アニメの発表からスタート。全国各地の海にまつわる民話25本をアニメ化し、これまでの作品とあわせてYouTube上で合計92本が公開されていることが紹介された。
トークセッションでは、登壇者たちがそれぞれ印象に残った作品を取り上げた。
高見沢さんは、北海道函館市に伝わる「ムイとアワビの合戦」を選び、「温暖化への警鐘が込められつつ、神様の知恵による解決が心温まる」と語った。
一方、佐藤さんは青森市の「善知鳥安方(うとうやすかた)」を紹介し、「丁寧な暮らしの描写が印象的で、アニメならではの表現力が活きていた」と述べた。
海野氏は「観音正寺の人魚伝説」(滋賀県近江八幡市)を取り上げ、現代的な資源管理のテーマや意外性のある人魚の姿に触れ、「考えさせられる作品だった」と話した。
音楽と民話が繋ぐ地域の記憶
高見沢さんは、過去に行っていた「フォークソング紀行」ツアーで訪れた土地の民話をもとに楽曲を制作していたことを紹介し、北海道乙部町の海の民話から生まれた歌詞を披露。その活動に対し、海野氏は「音楽と物語が結びつくことで、記憶に残りやすくなる」と評価した。
さらに佐藤さんは、THE ALFEEの楽曲「メリーアン音頭」に注目。盆踊りとしての可能性や、民謡が時代とともに形を変えて受け継がれていく点に触れ、「民話も民謡も、伝える力がある」と語った。
現代に生まれた新しい「海ノ民話」
トークの終盤では、登壇者が「現代だからこそ生まれる海ノ民話」を創作し、披露する一幕もあった。
高見沢さんが発表した「カモメのケジメ」は、海洋ごみに流れ着いたおもちゃの城を巣にし、カニたちが育てたカモメのひなが、恩返しとして助けに戻ってくる心温まる物語。
一方、佐藤さんは、環境の変化で寿司ネタが減ってしまった港町を舞台に、住民たちの努力と歌「お寿司節」によって町が再生する「かえってきたおすし」を披露した。
どちらの物語も、環境問題や地域の再生といった現代的なテーマを盛り込みながら、昔話の持つ普遍的な教訓や情緒を大切にしている。
「考える」ことから始まる未来の民話へ
イベントの最後には、2024年度の集大成として刊行される「海ノ民話学ジャーナル創刊準備号」の発表も行われた。
登壇者はそれぞれに感想を語り、高見沢さんは「創作が好きなので、民話をもとにした物語づくりにも挑戦してみたい」と今後の意欲を示した。佐藤さんは「アニメーションの力で、子どもたちにも民話が伝わりやすくなっている」とプロジェクトの意義を語った。
海野氏は、「意味がわからない民話も、自分で考えることで価値が生まれる。民話は考えるきっかけを与えてくれる存在だ」と話し、今後もプロジェクトを継続することを宣言。2025年度も新たに25本のアニメ制作を予定している。
海と人の関係を見つめ直し、次世代へとつなげる「海ノ民話」。過去の知恵と現代の感性が融合した新しい物語が、これからも生まれ続けることだろう。