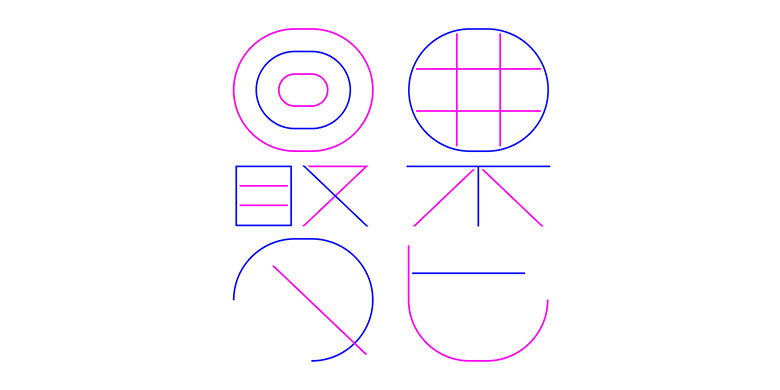最果タヒ(さいはて・たひ)
1986年生まれ。2006年、現代詩手帖賞受賞。2007年、第一詩集『グッドモーニング』(思潮社)刊行、同作で中原中也賞受賞。2014年、詩集『死んでしまう系のぼくらに』(リトルモア)刊行、同作で現代詩花椿賞受賞。2016年、詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(リトルモア)刊行、同作は2017年に映画化(監督:石井裕也)。
最新詩集は『恋人たちはせーので光る』(リトルモア、2020年)。初の絵本『ここは』(絵:及川賢治、河出書房新社、2020年)が6月25日に発売。
「これは詩だ」と意識するよりも先に、その言葉に出会ってしまう瞬間が増えてほしい
——昨年12月には〈HOTEL SHE,KYOTO〉とコラボレーションした期間限定のコンセプトルーム『詩のホテル』もオープンしました。読み手が本とは違う形で詩を楽しむ試みは、今後どのように展開させていければと考えていますか?

生活の中、町の中に詩がある、というのは、ずっとやってみたいことでした。詩を「これは詩だ」と意識するより先に、その言葉に出会ってしまうような瞬間が増えてほしいと思っています。不意打ちの出会いみたいなもの。それが詩であることさえもその人自身が気付くことがあってほしいと思う。誰にも何もいわれなくても。
そのときに、「詩だ」と言葉にならなくても、「この言葉がなんなのかわからないし、どう読んだらいいのかわからないのに、忘れられない」というような残り方ができたらと思っていました。それは、その人の奥にあるその人も知らない「わたし」が反応することであると思うから。

生活の中に溶け込んだ言葉だからこそ、「どう思うか」「どう感じるか」を考える時間を飛び越えてしまう。その人が把握していないところまで染み込むことがあるように思うんです。
『詩のホテル』はそういうコンセプトから佐々木俊さんが発想してくださったものでした。また、不意打ちでの言葉の出会いは、場を作るだけでなく、インターネットや雑誌、それから物でも実現できるのではないかと考えています。今は展示のグッズを準備中なんですが、生活の中に詩が紛れ込むような、そんなグッズが作れたらいいなと思っています。
書くことは、自分が知っている自分とは違うところまで連れて行ってくれる
——エッセイ集『「好き」の因数分解』(リトルモア刊)の中で、詩や小説を書く上での影響を受けた「好き」として、吉増剛造さんの詩や町田康さんの小説、BLANKEY JET CITYとNUMBER GIRLの歌詞などについて書かれていました。今、創作へのモチベーションや日々の活力となっている「好き」を挙げるとしたら、何になるでしょうか?
ものを書くことはむしろ今ニュートラルな時間として必要としています。喜びも悲しみも今は非常にストレスが高く、好きなものを求めるというよりは、これまで好きだったものを繰り返し聴いたり読んだりすることで、平熱を保とうとすることが多いです。
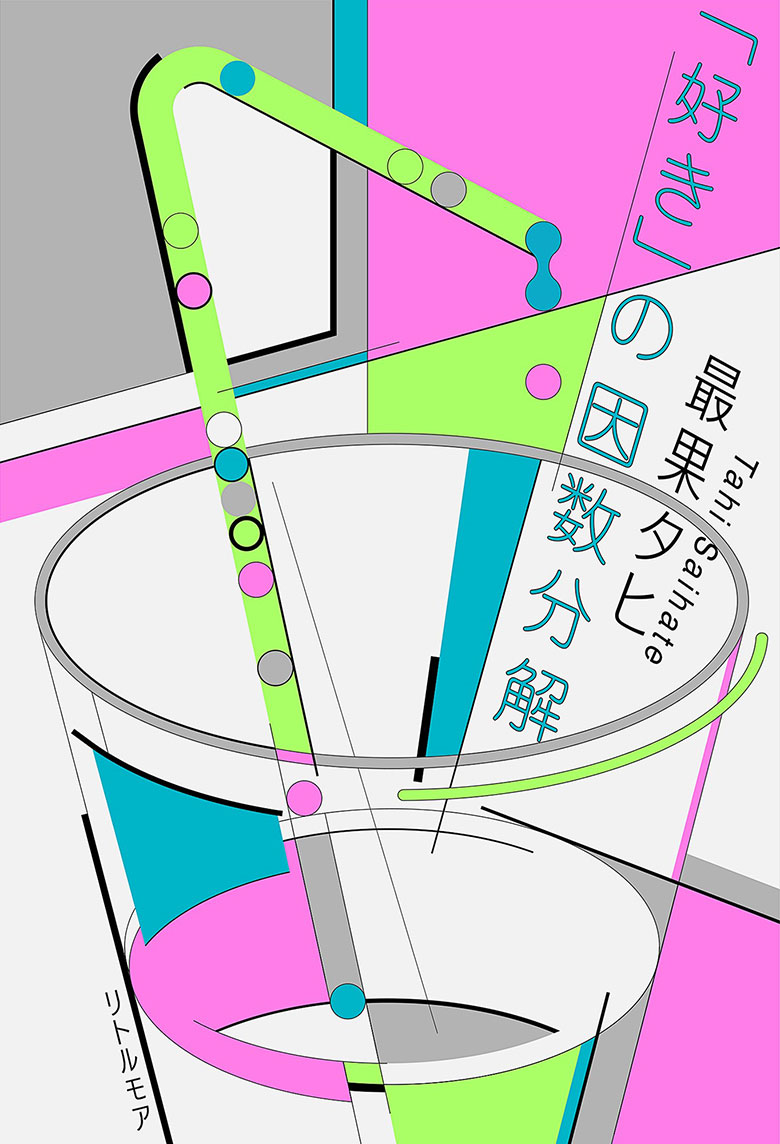
ものを書くこともその中の一つであると感じます。書いた瞬間に、「思ってもみない言葉が現れてテンションが上がる!」みたいなことはありますが、そうした平熱の中にある喜びは、ほかの喜びとはまた違って受け入れることができます。
今は、自分が自分の体を持つこと、自分でしかないことを、何度も思い出して意識しないと、自分ではないもっと大きなもの、不安や心配に飲まれてしまいそうになります。
個人として、一人の人間として不安であり続ける、心配をし続けるというのは、本当に難しいことで、つらいことで、だからこそ、自分より大きなものの一部として考えたいし、動きたいと思います。ただそうするとどうしても、自分じゃないはずの感情が頭の中で暴れて、ずっとしんどいんですね。24時間しんどくなる。
だから、過去に「自分だけがこれを好きなんじゃないか」と錯覚できてしまったような、それくらい好きなものを改めて聴く時間や読む時間をとっています。
書く行為も、自分一人でなければどうしようもないことで、でも、自分が知っている自分とは違うところまで連れて行ってくれる。大きくなるどころか0に近づくような瞬間だと思います。だから今は改めて、書くという行為を大切にしています。
——ネット上で詩作をはじめた2004年から、今年で16年が経ちます。詩作や文筆活動をするにあたって、原動力としてありつづけているものを挙げるとするなら何でしょう?
書いていると自分自身ではないものに出会う感覚があります。わたしは「自分の気持ちを書く」というようなことが苦手で、むしろ、「自分は自分でなければならない」「わたしはわたしの気持ちを吐露する存在である」ということを当たり前のこととして求められることがとても気持ち悪く、とにかくそんな世界から脱却したい一心でずっといます。

幼い頃から「きみはどう思うの」とか「気持ちを教えてくれてありがとう」とか、内側にあるものを吐露することが、深いつながりを作るために大切なんだ、とする考え方が苦手でした。
もちろんそうやって信頼を作ることが必要なひともたくさんいるとは思うのですが、私は人間が自分のことを全て把握できているとは思わないし、自分自身で吐露するものは、到底「深海」とは呼べない、浅いところの水だと思うんです。
人は怒りや優しさを発揮するとき、その全貌を自分で把握できるんでしょうか?わたしは、そうではないと感じます。自分が「本心」と思うもの、うちに隠していると感じるものを打ち明けることが、つながりを作るというなら、それは打ち明けるという行為そのものの勇気を称えているに過ぎない、と思います。
——感情をうまく言語化できないと、おいてきぼりにされてしまう不安を感じている自分としては、目から鱗が落ちそうです。
もちろん打ち明けたくて打ち明ける人もたくさんいるとは思うのですが、「自分の気持ちをもっと話してくれないと」とか、「信頼してよ」とか、言われると、どうしてわたしがしたくないことを、「親睦を深めるために」求めてくるんだろうと思ってしまう。
それを勇気がないとか、他者を信用してないとかでなじられるのはとても恐ろしいことです。こちらは勇気がないからそれをしないのではない。なぜ脱ぎたくない服を脱げと言われるのかわからない。
わたしは人間の建前や、人間のうわべの優しさも好きです。正直に思いを話すことがその人の本心であるとも思わないし、わたしはその人自身ではないので、むしろ、その人が気づかないことに気づきたいと思います。
人との関わり合いは本人が言語化できることを受け取ること以上に、本人では見えないものが見えるからこそ、のものであるように思います。
己を捨てて、言葉そのものになれる瞬間
わたしが言葉を書くとき、わたしのことを書こうとか、思っていたことを書こうとはあまり思いません。むしろ言葉の勢いに任せて書くとき、わたしはわたしが知らなかった言葉に出会う瞬間があります。
どこからそれが出てきたのか、どうしてこのタイミングで出てきたのかわからない、というような言葉が出たとき、わたしはわたしを捨てて、言葉そのものになれた気がするし、そういう言葉でなければ、読んだ人が、自分でも気付いていない意識の底まで届くことはないように思うのです。
この感覚は初めからずっと変わっていません。
インタビュー・テキスト:林みき/写真提供:株式会社リトル・モア、横浜美術館、河出書房新社、HOTEL, SHE KYOTO/企画・編集:田中祥子(CREATIVE VILLAGE編集部)