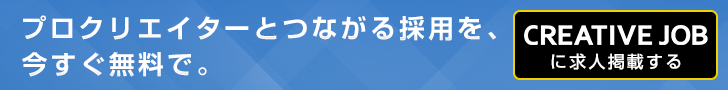GODIVA『日本は、義理チョコをやめよう。』やOK Go『I Won’t Let You Down』のMVなど常に斬新な視点で話題を集めている、原野守弘さん。以前、クリエイティブ・ビレッジでも取材をさせていただいた菱川勢一さんが監督を務められた、ドコモ『森の木琴』ではクリエイティブ・ディレクターとして作品に携わっていらっしゃいます。
今回の取材では、「クリエイティブに憧れた電通時代」「トップセールスマンからクリエイティブ・ディレクターへ」「クリエイターに必要な“マーケット審美眼”」の3つのテーマについてお話しを伺いました。
株式会社 もり
代表 / クリエイティブディレクター経営戦略や事業戦略の立案から、製品開発、プロダクトデザイン、メディア企画、広告のクリエイティブディレクションまで、広範囲な分野で一流の実績を持っている。電通、ドリル、PARTYを経て、2012年11月、株式会社もりを設立、代表に就任。
「OK Go: I Won’t Let You Down」「NTT Docomo: 森の木琴」「Honda. Great Journey.」「Polaリクルートフォーラム」「日本は、義理チョコをやめよう。Godiva」などを手がける。TED: Ads Worth Spreading、MTV Video Music Awards、D&AD Yellow Pencil、カンヌ国際広告祭 金賞、One Show 金賞、Spikes Asia グランプリ、AdFest グランプリ、ACC グランプリ、TCC 金賞、ADC 金賞、広告電通賞 最優秀賞、グッドデザイン賞 金賞、Penクリエイターアワード2017など、内外で受賞多数。
D&AD会員、NY ADC会員。2013年 D&AD 審査委員長、カンヌ国際広告祭 Innovation部門 審査員、2012年 カンヌ国際広告祭 T&I部門 審査員、Spikes Asia審査委員長、グッドデザイン賞 審査員。大阪芸術大学 客員教授。英国・Campaign誌の「The World’s Leading Independent Agencies 2014」にも選出された
早大の広告ゼミから電通へ―不本意な配属先で脱出の機会を伺う
広告業界を目指すキッカケになったのは、早稲田大学商学部のとあるゼミの存在でした。商学部の内容をあまり知らないまま推薦入試で合格したので、いざ入学してみると経理や経済の勉強ばかりでまったく興味を持てなかった。唯一ぎりぎり興味を惹かれたのが広告のゼミでした。消去法です。
当時は80年代のバブル絶頂期で、杉山恒太郎さんや糸井重里さんが大活躍してらした頃。広告業界への憧れもあったかもしれません。教授は日本の広告研究の第一人者で、小林太三郎先生(故人)という方。電通とのパイプも太く、先生のコネをフル活用して電通へ入社しました。
入社後は営業に配属される予定で、半年はマーケティング局で研修をしていました。しかしその後単なる人手不足が理由で、海外業務局という海外のメディアバイイングをする局へ本配属されました。
僕の主な仕事は、日本企業が海外で出す広告原稿をフェデックスで送る仕事でした。僕はまだ新入社員だったので有名な媒体ではなく、専門誌の担当。しかも、同じ原稿を流用する出稿ばかりだったので、正直とても退屈で、どうやったらこの局を脱出できるか、ということばかりを毎日考えていました。
偶然の重なりから、インターネット広告の牽引役に
 でも振り返って見ると、海外業務局に配属されたことが人生最大のラッキーにつながっています。ある日、担当だったパソコン専門誌の掲載確認をしていたとき、偶然その対向ページに「米国で世界初のバナー広告が登場した」というニュースを見つけたんです。それを見たとき、直感的に“未来”を感じました。1995年のことです。
でも振り返って見ると、海外業務局に配属されたことが人生最大のラッキーにつながっています。ある日、担当だったパソコン専門誌の掲載確認をしていたとき、偶然その対向ページに「米国で世界初のバナー広告が登場した」というニュースを見つけたんです。それを見たとき、直感的に“未来”を感じました。1995年のことです。
まだ日本でインターネットを知っている人はほとんどいない状態でしたが、僕はたまたま寮の隣の部屋に住んでいたGil KというDJからインターネットのことを教わっていました。
メールのアカウントも持っていたので、バナー広告を始めたばかりのYahoo!、Netscape、HotWired、AOLの4社に広告掲載に関する質問のメールを送ったんです。当時Yahoo!もまだ創業した直後でしたので、創業者のジェリー・ヤンからは感謝の返信と共に資料がすぐに送られてきました。世界の電通からの問い合わせですからね。
各社からの資料をまとめて文書にすると「海外業務局の原野君がインターネット広告に詳しいらしい」と社内で知られるようになりました。当時はAmazonも始まるか始まらないかくらいの頃で、インターネット企業のビジネスモデルは広告しかなかった。ですから電通社内でも感度の良い人はインターネット広告に注目していたんです。
ちょうど同じころ、孫正義さんが米国でYahoo!を買収し、日本でYahoo! JAPANを作ろうとしていました。そしてその広告枠を売るための会社をつくりたいと、電通に頼みにきたんです。そこで、インターネット広告に詳しい(らしい)ということで僕の名前が挙がり、現在のサイバー・コミュニケーションズ(CCI)を設立するプロジェクトを担当することになりました。24歳のころです。
数年後にドコモがiモードを始めたときも、直感的にこれはすごいことになると思ったので、すぐにCCIの事業計画書を焼き直して持って行き、電通とドコモの合弁でD2Cという会社を設立しました。このように黎明期のインターネット広告の世界に身を置けたのはラッキーでしたね。
広告業界、メディア業界の人脈も増え、セールスマンとして有名にもなってきた頃“ドットコムバブル(インターネットバブル)”が起きました。一緒に仕事をしていた人たちが、ストックオプションで次々と億万長者になっていく。“ヒルズ族”と呼ばれるような人達が出てきた頃でした。
そんな様子を間近で見ていたら「もちろん自分も…」と若気の至りで金に目が眩み(笑)、電通を辞めたんです。
拝金主義からの生還―『広告批評』を目指して
 そうして28歳の頃、ネット広告会社の役員になり上場もしたのですが、IT業界の拝金主義的なカルチャーが感覚的に肌が合わず、電通へ戻ることにしました。
そうして28歳の頃、ネット広告会社の役員になり上場もしたのですが、IT業界の拝金主義的なカルチャーが感覚的に肌が合わず、電通へ戻ることにしました。
戻った後は、またしばらくインターネット広告のセールスマンをやっていたのですが、ある日書店で手に取った『広告批評』にCMプランナー・権八成裕くんのインタビューが載っていて、それを読んだときに次の転機が訪れました。
当時の『広告批評』は、毎回有名なクリエイターのインタビューが載っていて、次のページには芸能人のインタビューがあるという感じで、クリエイターがタレント扱いされていた。そこで権八くんは佐々木宏さんのことを「ヒロシ」と呼び捨てにしていた。
年功序列の厳しい媒体セールス担当の僕から見たら、それはロックスターのようなかっこよさに見えた。そこで「僕も『広告批評』でインタビューされたい」というかなり不純な動機と野望で、クリエイターに転身しよう、と決意しました。
電通にはクリエイティブ局に移るためには難しい試験があり、かつ僕はその受験資格の年齢を超えていました。そこで上司だった杉山恒太郎さんに裏ルートはないかと相談したんです。すると、「君は会社作るのが得意だから、クリエイティブブティックをつくってそこに出向したら“クリエイター”だよ」という詭弁のような助言をされて、ドリルを設立しました。
念願のクリエイティブ分野の仕事。しかし、最初の2?3年はほぼ全てのプレゼンで負けていましたね。
また日本のクリエイティブ業界は典型的なムラ社会で、国内の広告賞は仲間内で賞を回しあっているようにしか見えなかった。自分のように媒体局出身で、なんの経験もコネもなく、30代からクリエイティブを始めた人なんかはまったく相手にされない空気でした。
そこで目標を海外の広告賞に絞ることにして、海外作品が掲載されている広告賞の年鑑を、修行のようにひたすらディープラーニングするということをしばらく続けました。この経験がいま、とても生きています。
“商品開発や流通方法まで考える”―それが原野流クリエイティブ
 そんな中でもターニングポイントの1つになったのは、タカラトミーの“リカちゃん40周年記念広告”の仕事でした。僕はただの周年広告を作るのは意味がないと思ったので、商品開発も含めた、新しいキャンペーンの手法を提案しようと考えました。
そんな中でもターニングポイントの1つになったのは、タカラトミーの“リカちゃん40周年記念広告”の仕事でした。僕はただの周年広告を作るのは意味がないと思ったので、商品開発も含めた、新しいキャンペーンの手法を提案しようと考えました。
この時発見したインサイトは、リカちゃんの遊びは全部“家事労働シュミレーション”ではないか、ということでした。女の子は結婚して子どもを生んで良いママになるのが一番だよ、というジェンダー的なステロタイプでリカちゃんの世界ができている、ということに気づいたのです。
しかしながら、さすがにそれはもうこの21世紀では通用しない。そこでテーマを“新・女の一生”と決め、子供だけでなく、現代の働くお母さんも一緒に楽しめる体験をテーマにした新シリーズを立ち上げる、という企画を思いつきました。家事労働シミュレーションではなく、“世界旅行”をテーマにしたらどうだろうか、と。
それが、“リカ・ワールドツアー”という企画。リカちゃんが世界中を旅して、一人の自立した女性に育っていく物語。その模様は、リカちゃんが毎日ブログに書いて報告する。
リカちゃんがパリに到着すると、実際に店頭では「リカ・イン・パリス」という、パリのデビュタント・ファッションの商品が発売される。LAではセレブ・ファッション、ナイロビではサファリルック、というように都市ごとの特徴をふまえた新商品をつぎつぎと発売していきましょう、という壮大なキャンペーンを提案したんです。人形の洋服のデザインや、飛び出す絵本がドールハウスになる、というような細かいアイデアまですべて考えて提案しました。
クライアントもすごく気に入ってくれて、このアイデアをほぼ全面的に採用してくれました。このキャンペーンを全部やりきったことで自信もつきました。
そのころから別の仕事でカンヌを受賞したりもして、ぽつぽつと指名の仕事もいただけるようになり、念願の『広告批評』でのインタビューも実現しました。
『森の木琴』がわたしたちの眼に映るまで
『森の木琴』が生まれたのは、そのような流れのなかでドコモのコンペにも呼ばれるようになったことがきっかけです。これはもしかしたら、菱川さんも知らない話かもしれないけれど、元々はWebと新聞広告のキャンペーンで最初は別の企画で決定していました。それが予算の関係でボツになり、急遽企画したのが、『森の木琴』です。
もともとあの動画はWeb上のお楽しみコンテンツにすぎなかったので、制作者が好きなように作って最後にクライアントに見せたという感じでした。クライアントさんは試写を見てすごく気に入ってくださり、最終的にTVCMにすることになりました。
ところが、肝心の公開日が東日本大震災と重なってしまい、キャンペーンはすべて中止になってしまったのです。ただ、YouTubeにアップしておいた動画を下げ忘れていたのが、偶然『NYタイムズ』の記者の目にとまり、同紙の記事から世界中に拡散され、逆輸入的に日本でも話題になりました。カンヌでもゴールドを獲得し、またひとつ自信になりました。
本当の広告づくりとは―“販売促進”と“広告”は違う
 直近で手応えのあった仕事としては、POLAやGODIVAの広告があります。
直近で手応えのあった仕事としては、POLAやGODIVAの広告があります。
カンヌ受賞作品を見た業界の人がよく「この広告で売れるのかな」と上から目線で茶々を入れることがありますが、その問いそのものが間違っている。そもそも“広告”の目的は、商品を売ることではないんです。
海外では商品を売ることが目的のものは“販売促進”という別ジャンルで認識されていて、販売促進と広告は別物とされているんです。“広告”の目的はブランドを好きになってもらったり、尊敬してもらったりするためのもの。
結果として商品が売れることもあるんですが、それは目的の本質ではない。それが“広告”なんです。
日本で流れている多くの広告は、販売促進だと思います。それだから、広告と販売促進を混同して「この広告で売れるのか?」というような問いを発してしまう。僕は、“広告”をディープラーニングして実績をつくってきたので、販売促進よりも“広告”の可能性を信じています。
POLAやGODIVAの広告は、直接的には商品を売ろうとしていないけど、ファンを増やすことで結果的には売り上げ増にもつながっている。これからも“広告”をつくる、ということは大切にして頑張っていきたいですね。
また、過去の名作に敬意を払いつつ、そこに何が“お返し”できるか、ということも重要です。新しい制作手法というのは、“お返し”の一つになります。例えば、OK Go『I Won’t Let You Down』のミュージックビデオ撮影。「まだ世界で誰もやっていない、ドローンの使い方をしよう」ということで約5分間のMVをワンカットで撮りました。
これは、バスビー・バークレーという1930年代を中心に活躍した監督・振付師の作品を、ドローンという最新撮影手法でとらえ直したものといえます。人類の財産である名作に「新しいことをお返しできるかどうか」と考えた結果できた作品でした。
クリエイティブ・ディレクターに必要なのは“マーケット審美眼”
広告の仕事は当然ながら自己表現ではなく、目的にあったものを作るビジネスです。この“客観性”があるかは、この広告業界で重要な資質のひとつだと思います。自分の企画を、世の中の大多数の人がどう見るかという“マーケット審美眼”で見られるかどうか、ということです。
その最終責任者が、僕のやっている“クリエイティブ・ディレクター”という仕事です。マーケット審美眼を磨くためには、高校生から大学生ぐらいまでの間に良質なクリエイティブをその反響も含めてディープラーニングする必要があると思います。
海外の広告賞の審査員をすることもあるんですが、最終的に評価される作品は“強さ”がポイントです。インパクトの場合もあるし、感動の場合もあるし、新しさの場合もある。強さにも色々種類はありますが、他のものとは違う、抜きん出る“強さ”があるかどうかが一番大事。
僕がやってきたことでお勧めできるのは、海外広告賞の受賞作品をディープラーニングすること。ただ見るだけではなく、自分なりの原理を発見しようという気持ちで、「これは何でイケてるんだろう」と分析しながら見ることがポイントです。
日本の若いクリエイターへ
今、若い人で広告の仕事がやりたいのなら、海外に目を向けたほうがいいのではないか、と強く思います。特に年齢が若い人ほど、「自分の職場は日本でいいのか?」ということを真剣に考えたほうがいい。
30年後の日本は人口が4000万人くらい減少すると言われていますから、クリエイティブ業界も含めて全産業が縮小傾向にあります。しかもその中でコピーライター、アート・ディレクターの著名人が存命している限りチャンスも限られる。
一方、中国の広告業界でグローバルブランドを扱うところは、クライアントも代理店もほとんど英語で仕事をしています。日本より遥かに国際的です。外資のエージェンシーに入って、転勤で行くチャンスを探すことも一つの道でしょう。
コピーライターだと言葉を扱うので厳しいかもしれませんが、Web企画やプログラマー、デザイナーなどなら、中国に限らず、その分野で成長している国へ行って仕事をしたほうが絶対良いと思います。
インタビュー・テキスト:上野 真由香/撮影:SYN.product YUICHI TAJIMA/編集:CREATIVE VILLAGE編集部